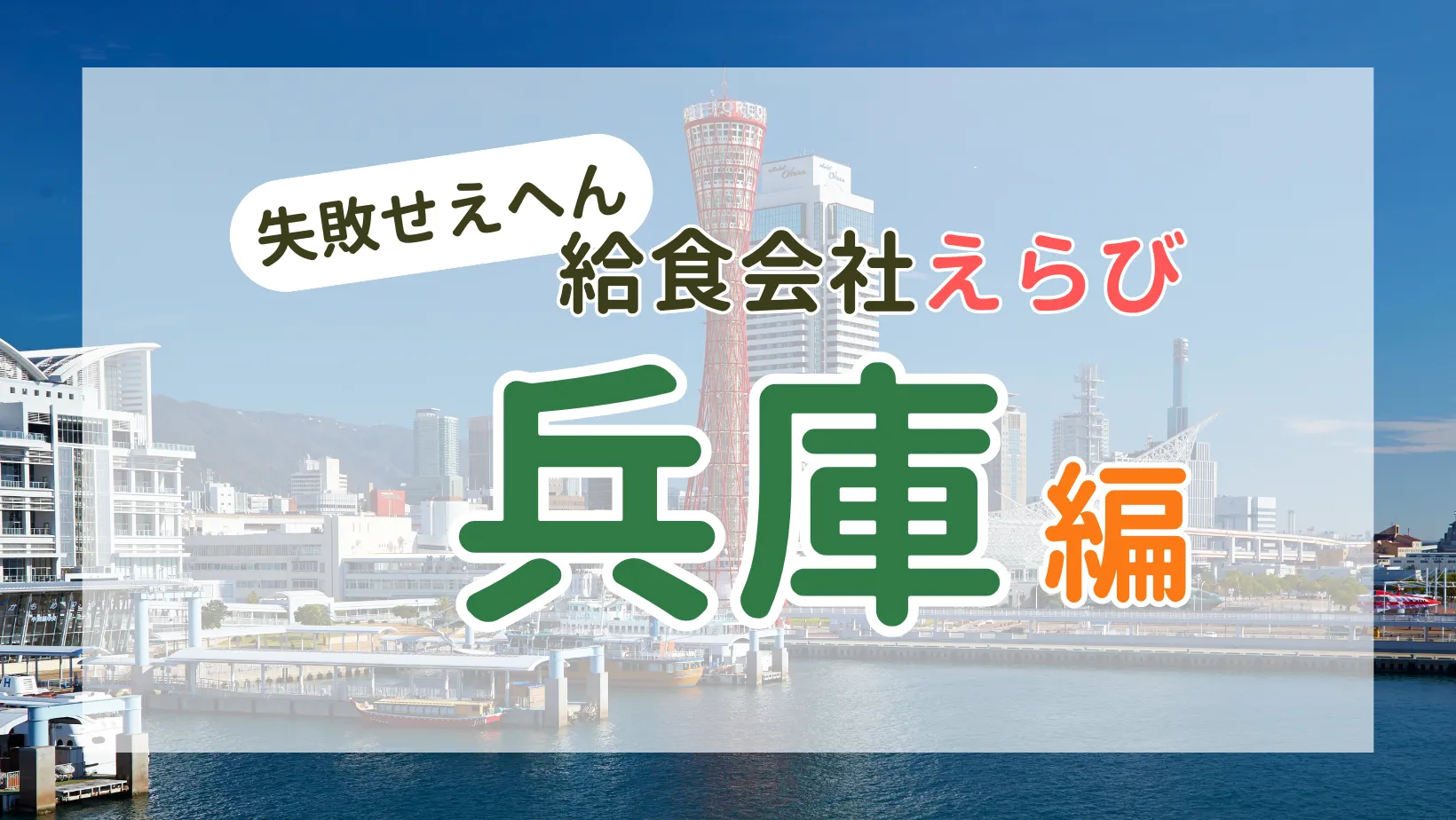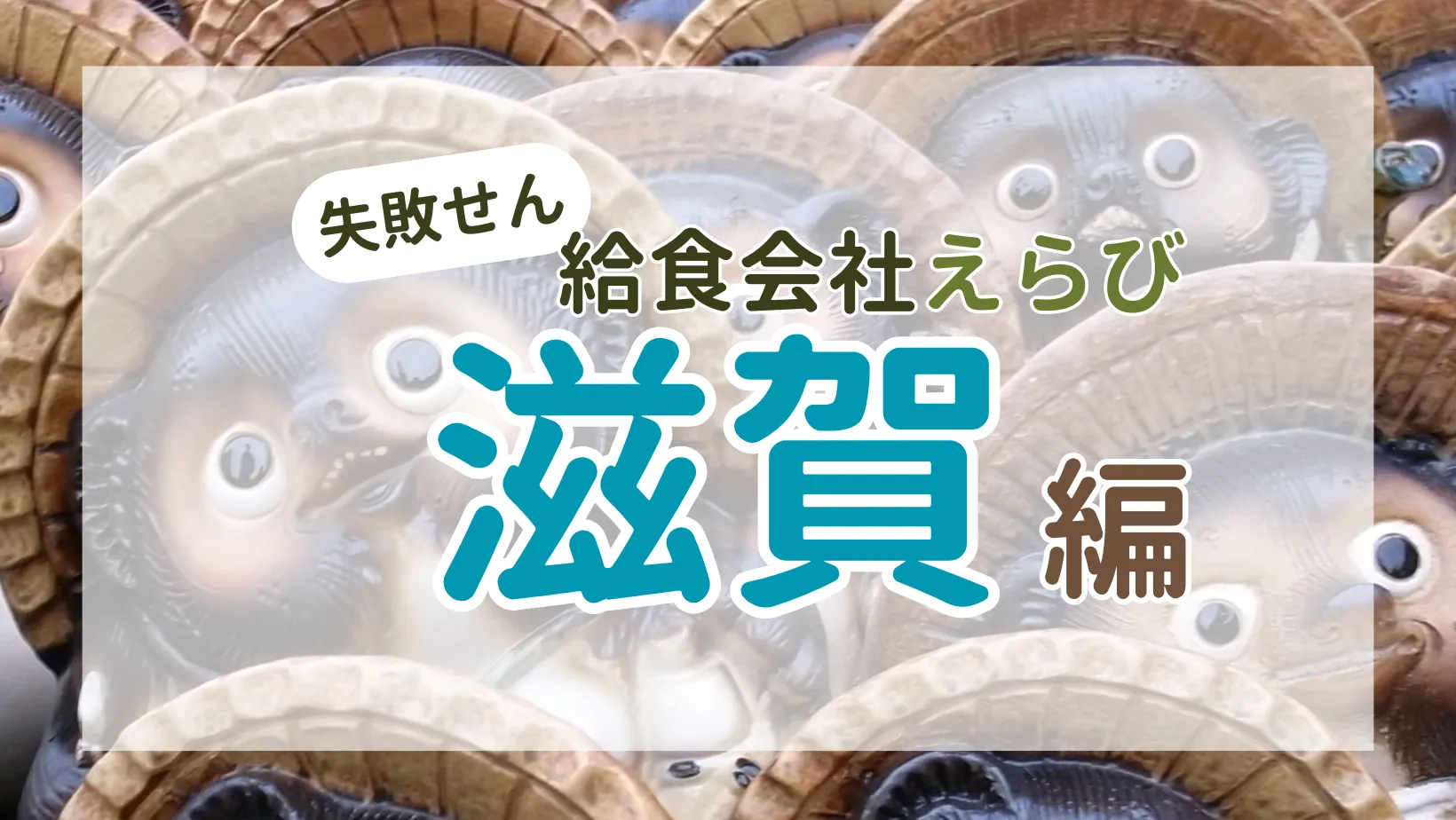【2022年の恵方は北北西!】節分の発祥を探る!節分の日の給食メニュー(保育園・高齢者施設)もご紹介

節分といえば豆まきをしたり、恵方巻きを食べたりするイメージですが、
その発祥や豆をまく理由などをご存知でしょうか?
今回は節分行事の発祥をはじめ、節分でおなじみの豆まきや恵方巻き、
鰯の頭を飾ることにどのような意味が込められているのかお伝えしていきます。
さらに、保育園や高齢者施設などで名阪食品が提供している節分の日の献立もご紹介。
園児様やお客様に喜んでもらうために、さまざまな工夫を凝らしています。
この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム
名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。
編集方針はこちら
1.節分とは?
保育園や高齢者施設でも恒例イベントとなっている節分。
節分とは「季節を分ける」という意味合いで、
立春・立夏・立秋・立冬の前日を指して使われていた言葉です。
立春の節分が旧暦の大晦日にあたることから、
やがて新年の厄災を祓うための伝統行事へと発展していきました。
そして江戸時代以降には、
節分が現代と同様に立春の節分のみを指す言葉として使われるようになったのです。
(1)節分の発祥
節分の発祥については、季節の変わり目に鬼や邪気が出るとされた昔からの言い伝えが関係しています。
当時は災害や飢饉、大病などの厄は鬼や邪気がもたらすものと考えられていました。
中国では、鬼や邪気を祓うために「追儺(ついな)」と呼ばれる儀式が行われるようになり、
疫病が大流行していた奈良時代に日本にも伝わりました。
このときに宮中で行われた追儺が節分の始まりとされています。
加えて平安時代には、陰陽師(おんみょうじ)による宮中の鬼祓いが盛んとなり、
節分の行事が広く世間に伝わっていきました。
そして、江戸時代には一般庶民も節分の行事を行うようになったのです。
節分行事は今もなお、その年の健康と幸せを願い行われています。
ここからは、節分でおなじみの豆まきや恵方巻き、鰯の頭を飾る儀式の意味ややり方を見ていきましょう。
(2)豆まき
「鬼は外! 福は内! 」というおなじみの掛け声の通り、豆まきは、邪気を追い払って新年に幸運を呼び込むために行う儀式です。
大豆には穀霊が宿るとされる古くからの言い伝えがあります。
さらに、豆は「魔滅(まめつ)」、煎った豆は「魔の目を射る」の意味合いで、
鬼にめがけて煎られた大豆を投げるようになったといわれています。
【一般的な豆まきの方法】
鬼がやってくる夜に家中の窓や扉を開け、
大きな声で「鬼は外! 福は内!」と言いながら、家の中や外に向かって大豆をまきます。
豆まきが終わったら、家に再び鬼が入ってこないように開けていた窓や扉を閉めます。
そして最後に翌年1年間の無病息災を願って、年齢よりも一つ多い数の大豆を食べましょう。
(地方によっては、大豆を食べる数を満年齢にするか数え年にするかが異なります)

(3)恵方巻を食べる
恵方巻の発祥にはいくつか説があり、
そのうちの一つとして挙げられるのが江戸時代~明治時代における大阪の花街です。
元々恵方巻ではなく「丸かぶり寿司」または「太巻き寿司」という呼び名でした。
太巻きを食べて節分を祝い、商売繁盛を願う形で始められたようです。
恵方巻の文化は戦後に廃れていきましたが、
1970年代には海苔問屋が海苔のPRを目的に活用し、再びその文化が復活しました。
関西圏の文化であった恵方巻ですが、コンビニチェーン店の促進により、
今では全国に伝わり、節分の行事食として定着しています。
一般的な恵方巻の食べ方
一人一本の太巻きを用意し、縁や福を途切れさせないため、包丁で太巻きを切らないようにします。
その年の福徳を担う歳徳神(としとくじん)がいる方角で、
なおかつ何事にも吉とされる“恵方”を向きながら食べましょう。
恵方巻を食べるときに喋ってしまうと運が逃げていくため、
最後まで無言で食べきるのが良いとされています。
(4)鰯(いわし)の頭を飾る
節分には、豆まきや恵方巻のほかに、焼いた鰯の頭を柊の枝に刺して飾る風習があります。
地域によって「焼嗅(やいかがし)」や「柊鰯(ひいらぎいわし)」とも呼ばれます。
鰯の匂いで鬼を寄せつけず、柊の棘で鬼を追い払う意味で行われているのです。
鰯の頭のみが使われるため、鰯の身を節分の行事食として食べるケースも多く見られます。
一般的な柊鰯のやり方
鰯の頭を飾るのは、豆まき・恵方巻の儀式が行われる節分の夜です。
飾る場所は玄関と決まっていて、鬼が家のなかへ入るのを防ぎます。
柊鰯は節分の夜だけ飾り、翌日には片付ける場合が多いですが、2月末まで飾ったり、
節分よりも早い小正月から飾ったりする地域もあります。
鰯は匂いが強い食材であるため、飾っている間に鳥や猫に荒らされないように注意が必要です。
処分する場合は、神社にお焚き上げをお願いするか、お酒や塩で清めた後に包んで捨てると良いでしょう。

2.名阪食品の献立紹介
名阪食品では、幼稚園や保育園、福祉施設の利用者様に楽しんでもらえるよう、
旬の食材や四季折々の行事を取り入れたメニューの提供を行っています。
ここでは、節分メニューをご紹介していきます。
(1)保育園・幼稚園
幼稚園や保育園での節分メニューとして、恵方巻はもちろん、
鬼の形をしたクッキーやゼリー、鰯を使った料理などを提供しています。
ほかにも可愛らしい鬼に見えるように具材を盛り付けるなど、
園児様に喜んでいただくために工夫を凝らしています。
【鬼の顔をイメージしたゼリー】
(2)福祉施設
施設の利用者様に向けたメニューでは、巻き寿司やいなり寿司が登場します。
ほかにも、茶碗蒸しやお吸い物など、巻き寿司のお供にもぴったりの料理をご提供。
栄養バランスに配慮したメニュー且つ、節分ムードが楽しめる内容となっています。

【鰯ミンチを使ったパスタ】
3.年に一度の節分。給食でも楽しみましょう!
名阪食品では、節分行事が楽しめる給食メニューも提供しています。
節分は、健康や幸せの願いが込められた、古くから受け継がれてきた行事です。
今回紹介した豆まきや恵方巻、柊鰯のそれぞれの意味を知れば、
より気持ちを込めて節分行事を行えるのではないでしょうか。
まわりの方にも節分の意味を伝え、一緒に今年の節分を楽しんでみてくださいね。
名阪食品では、節分行事が楽しめる給食メニューも提供しています。
多彩な行事食を提供できる給食委託会社をお探しの方は、下記よりぜひお問合せください。
無料資料ダウンロード

サンプル献立を
ダウンロードいただけます

こちらの導入事例資料を
ダウンロードいただけます