【プロ監修】介護報酬の改定で何が変わる?施設運営者が押さえるべきポイントも解説


監修 山中美緒子
株式会社RICCIO CEO
(https://riccio-consulting.jp/)
総合病院等での看護師、または感染管理認定看護師としての経験を元に感染対策・運営支援・教育支援など介護事業所の安全・安心のためにコンサルティングさせていただいております。
新年度になるとさまざま制度が新しく始まります。介護分野も例外ではありません。たとえば、事業者が利用者に提供した各種介護サービスの対価として受け取る介護報酬もそのひとつ。
介護報酬は3年ごとに見直されており、2024年度からは新しい介護報酬が適用されることになっています。介護報酬がどのように改定されたのか概要を知り、改定されることで起きる変化について知りましょう。
※また合わせて、サイト内におきまして「高齢者施設 お悩み解決」に関する記載もご用意しております。是非ご参考下さい
1.2024年度介護報酬改定の改定率は?
冒頭でも紹介したように、介護報酬とは事業者が提供した各種介護サービスの対価のことです。事業者は保険者である市区町村から介護報酬を受け取ります。介護報酬は介護保険報酬点数表をもとに算出され、厚生労働省において3年ごとに見直されます。
では、介護報酬はなぜ定期的に見直されるのでしょう? それは、介護サービスの質を確保するためです。介護需要や経済状況、政府の政策の変更を踏まえその時代に合った介護報酬にする必要があるのです。
2024年度の介護報酬改定の改定率は、「+1.59%」となりました(※1)。+1.59%の内訳は、介護職員の処遇改善が0.98%、介護職員以外の処遇改善等が0.61%です。
なお、処遇改善の一本化による賃上げ効果や光熱水費の基準費用額が増えたことで介護施設は増収が見込まれます。さらに改定率の外枠での引き上げは+0.45%、実際には2.04%(1.59%+0.45%)相当の改定になると考えられています。
(1) 介護報酬改定はいつからはじまる?
介護報酬改定の施行日はサービス種別によって異なり、2024年4月1日と2024年6月1日に分かれます。2024年6月1日から施行されるのは「訪問リハビリテーション」「訪問看護」「居宅療養管理指導」「通所リハビリテーション」の4つです。それ以外のサービスは、2024年4月1日に施行されます。
2.2024年度の介護報酬改定のポイント
前述したように、社会の変化や利用者のニーズに合わせて介護報酬は定期的に改定されており、そのなかで介護サービスの適切な提供と利用者のQOL向上が進められています。
2024年度介護保険報酬改定も、大きな目的を見据え実施されました。たとえば、団塊ジュニア世代が65歳以上となり高齢者人口がピークを迎える2040年に備えること。そして、人材不足や介護職員の待遇改善を進め、介護事業従事者の働く環境を整備することなどが挙げられます。
最新の介護保険報酬改定の目的や内容を知り、施設運営者や介護職員に何が求められているのかを知るためにも、今回の介護保険報酬改定のポイントを見ていきましょう。
65歳以上の高齢者は2025年ごろから増加傾向にあり、2040年ごろにピークを迎えると考えられています。これにより認知症や単身の高齢者が増加するなど、介護サービスの需要が増大することが見込まれます。
こうしたなか求められているのが、住み慣れた地域でこれまでと同じような生活ができるようにすることです。これを実現するには、質の高いケアマネジメントや実情に合わせた柔軟な取り組みが必要となるでしょう。その一環として、今回の改正では以下のような取り組みに触れられています。
|
・質の高い公正中立なケアマネジメント ・地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取り組み ・医療と介護の連携推進 ・看取りへの対応強化 ・感染症や災害への対応力向上 ・高齢者虐待防止を推進 ・認知症の対応力向上 ・福祉用具の貸与や特定福祉用具販売の見直し |
介護保険は、介護が必要になった方が自立した日常生活を送れるよう、それぞれに適したサービスを提供することが目的です。しかし、必要なサービスを提供するだけでは、症状が悪化し重度化する恐れも。そうなってしまうと、介護保険が破綻しかねません。
そこで求められるのが、利用者の自立支援や重度化を防ぐ取り組みです。具体的には以下のようなものがあります。
|
・リハビリテーションや機能訓練、口腔、栄養の一体的取り組み ・自立支援や重度化防止に係る取り組みの推進 ・科学的介護情報システム(LIFE)を活用した質の高い介護 |
リハビリや機能訓練によって自立を支援し、口腔管理や栄養管理をすることで健康へと導く取り組みも呼びかけられています。また、在宅復帰を促して在宅療養支援機能を充実させる取り組みも実施。科学的介護情報システム「LIFE」も用いるなど、利用者のデータと組み合わせてエビデンスに基づいた高い介護を提供することが、求められています。
③良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
介護業界では長年人材確保が課題となっており、人材流出も起きています。他業種の賃金引き上げが進んでいるため、今後はさらなる人材不足が懸念されるでしょう。高齢化が急速に進んでいるため、良質なサービスを提供するためにも人材確保は急務と言えます。
今回の改定では、人材確保に向けた問題解決として具体的な取り組みも呼びかけられています。
|
・介護職員の処遇を改善 ・生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり ・効率的なサービス提供の推進 |
介護ロボットやICTを活用した介護助手の導入、テレワークなどが推奨されており、人材確保や働きやすくなる職場環境づくりにつながることが期待されます。
介護保険料や公費、利用者の負担によって介護保険制度は成り立っています。そのため、若い人から高齢者まですべての世代が安心して利用できる制度でなければいけません。これからは、介護保険制度を安定的に持続するための制度づくりが必要となるでしょう。
2024年度介護保険報酬改定では、ムダを省きつつ適正な評価をする、そして必要なところに必要なサービスを提供するため、評価の適正化・重点化として以下のような取り組みが呼びかけられています。
|
・理学療法士などの訪問看護評価の見直し ・短期入所生活介護における長期利用の適正化 ・訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬見直し ・同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント ・モニタリング実施時期の明確化 ・多床室の室料負担 |
また、報酬の整理・簡素化として基本報酬の見直しや一部加算の廃止などの検討により、複雑な報酬体系を改めわかりやすく整理することで、利用者の負担に配慮しつつ介護職員に適正な報酬を渡すことも、今回の取り組みとして挙げられます。
利用者が快適に適切なサービスを受けるため、また介護職員がより働きやすくなるためには、そのほかの諸制度の見直しも必要でしょう。
たとえば、重要事項の書面掲示をインターネット上で閲覧できるようにする、送迎時にほかの事業所の利用者と同乗を可能とするなど効率的な運営ができるような工夫が挙げられます。そのほかにも昨今の光熱・水道費上昇を加味して居住費を見直すなど、さまざまな取り組みが考えられています。
3.改定ポイントを参考に職場づくりを
2025年以降は団塊の世代が後期高齢者になり、介護需要が爆発的に増加することが予測できます。今回のような介護報酬改定が行われるときは、報酬計算の方法が変わったり新しい設備を導入する必要が出てきたりするなど、介護事業所の運営方法が大きく変化することもあります。時代の流れや需要によって柔軟な対応が求められるため、改定に合わせて職場環境づくりに努める必要があるでしょう。
無料資料ダウンロード
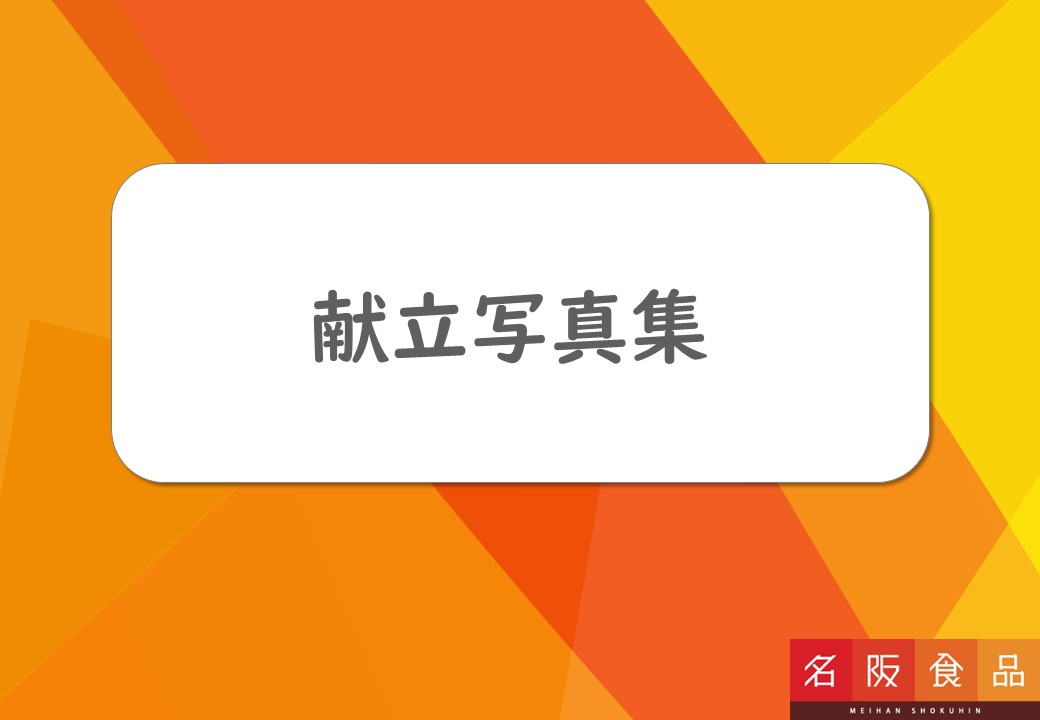
献立写真集の資料を
ダウンロードいただけます

キラッと光るレシピ集の資料を
ダウンロードいただけます
無料資料ダウンロード
【出典】
※1厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」







