止まらない物価高!給食現場でできる対策とは

2022年に入り、物価上昇が続いています。総務省の発表によると、2022年9月の消費者物価指数は3%の上昇(※1)を見せており、なかでも食材価格や光熱費の高騰は、教育機関や介護施設などの給食現場を直撃しています。
まだしばらくは続くと見込まれる物価上昇。給食現場では、今後も対策を講じていく姿勢が求められています。そこでこの記事では、物価高の要因や給食現場でできる対策について紹介していきます。食材の値上がりに悩まされている教育機関・介護施設などの給食現場の方の、参考になれば幸いです。
※また合わせて、サイト内におきまして「高齢者施設 お悩み解決」に関する記載もご用意しております。是非ご参考下さい。
この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム
名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。
編集方針はこちら
1.物価高の要因
近年の物価高には、主に次の3つの要因があると言われています。
(1)コロナの影響
物価高の要因の一つは、世界的に流行している新型コロナウイルス感染症です。
さまざまな制限を余儀なくされたコロナ禍の影響を受け、港湾の人手不足などが発生し、世界的な物流コストが上がっています。食料自給率が低い日本にとって、これらのコスト上昇が与える影響は小さくないでしょう。
また、世界経済はすでにコロナから回復しつつあることから、食料品などの需要が拡大しています。一方で、異常気象が重なり、需要に対して供給が追いついていないことも物価高に拍車をかけている要因と言えるのです。
(2)ウクライナ情勢の影響
コロナ禍に加え、物価高の要因となっているのがウクライナ情勢です。
ロシアのウクライナ侵攻により、原油や穀物の供給に大きな影響が出ています。特に、ウクライナ産のひまわり油の価格が高騰したことから、代替品として菜種油の需要が急増しました。この変化は、これまで菜種油を使ってきた飲食店などで大きな打撃となっています。
また、ウクライナとロシアが世界の輸出量3分の1を占める小麦の供給が減少したことで、パスタやパンなどの価格が高騰。加えて、世界の輸出量の2割を占めるトウモロコシの供給量減少によって、畜産業では餌代が上がったため、食肉も高騰しています。
さらに、ロシアへの経済制裁の影響から原油の供給量が減ったことで、燃料費も上昇しています。こうした物流や包装などの価格が上がっていることも、物価高の要因です。
(3)円安の影響
日米の金利差が広がったことにより、円安が進んでいることも物価高に影響しています。
2022年11月時点では、日米の金利差を縮小する動きも高まり、円相場は一時値上がりを見せました。しかし、すぐに買い戻しが起こるなど、荒い値動きが続いています。食品の大部分を輸入に頼っている日本にとって、こうした円安は物価上昇に拍車をかける要因となっているのです。
このような食品やエネルギーを中心とした物価高は、今後も続くと考えられます。帝国データバンクによると、2022年中に値上げされる食品は2万品目超え、平均値上げ率は14%となる見込みとのこと(※2)。断続的な値上げは、来年も続く可能性があると示唆されています。
2.給食現場の状況
長引く物価高の影響を受け、給食現場ではどのような変化が起きているのでしょうか。学校給食、介護施設の現状について見ていきましょう。
学校給食では
野菜の値上がりに続き、給食に欠かせない肉も1割ほど価格が上がっています。
肉はもともとの単価が高いため、たとえ1割の値上げでも大きな影響です。昨年度と同じ給食を出すと、一日あたり約10万円余分に費用がかかるという給食センターもあります。そのため、予算を超える日にはデザートなどの品数を減らす、安価な食材を活用するなどの対応を図るところも増えています。
また、給食費の値上げに踏み切る自治体も少なくありません。東京23区のなかには、給食費を値上げし、その分の費用を全額または一部公費負担としている区もあります。文部科学省は、物価高騰による給食費の値上がりで保護者の負担が大きくならないよう、臨時交付金を活用した支援策の推進を各自治体に改めて求めています。
老人ホームなどでは
社会福祉法人の経営動向を調査したデータによると、2022年4月から6月までに、物価高騰によって45.5%の施設で給食費が増加したといいます。また、全国社会福祉法人経営者協議会が2022年6月に厚生労働大臣に提出した要望書によると、国の物価上昇率(105%)以上の給食費・食材費の上昇が27%の施設で見られたと示されました。
そのため、やむなく食材の質を落とす、給食費の値上げを図るといったケースも増えているのです。
3.給食現場でできる物価高への対応
今後も続く物価高への対応として、給食現場では次のような工夫を凝らすところが増えています。
予算に合わせた食材を選ぶ
穀物類や油など、高騰している食材は提供回数などを見直し、予算に合った食材を選ぶ施設が増えています。たとえば、牛肉の代わりにさつま揚げを提供したり、高騰するキュウリの代わりに茎わかめを使用したりする施設もあるようです。
また、味付きのパンから割安のロールパンへ変更、鶏モモ肉を胸肉に変更するなど、予算を圧迫しない食材に置き換える工夫を行うところもあります。栄養価を損なわずに満腹感が得られるよう、量や食材を選ぶ努力が続いています。
名阪食品でも、加工済みの材料を使用しないことでコストダウンを実現。原材料から作成したり、作業動線を見直したりするなど、値上げをしないような工夫を図っています。
補助金を活用するケースも
自治体によっては、物価高騰対策として補助金での支援を行うところもあります。
たとえば栃木県栃木市では「学校給食物価高騰対策事業」として、一人当たり27円の食材費の補助を行うことを公表しました。茨城県の大洗町でも2022年11月から2023年3月まで、給食費の給付金を支給することが決定しています。
また、千葉県松戸市では「介護施設等における原油価格物価高騰対策支援補助金」をスタート。燃料費および光熱費経費について、一事業所当たり10万円を上限とする支援策を2022年11月1日より開始しました。各都道府県や市町村でこうした支援が活発化しているため、今後はこれらのサポートを活用することもできるでしょう。
仕入部の工夫
メーカーからあらかじめ値上げ依頼があった場合、油など日持ちする食材を値上げ前に一括で仕入れておくことで仕入れ価格を抑えるという方法があります。名阪食品でも、「大量購入する代わりに仕入れ価格を安くできないか」とメーカーと交渉を行うなど、少しでも安く仕入れられるような工夫をしています。 
人件費の削減
食材の価格が上昇している一方で、2022年には最低賃金が引き上げられました。そのため、手作り給食には食材費が安く済む一方で、調理に時間と手間がかかり人件費が増加するという課題も生じているのです。ただしこの場合も、効果的に調理済み食品を取り入れることで人件費を抑えることができます。
名阪食品では、現場調理と厳選されたクックチル食品を効果的に組み合せた新しい給食の形として「ハイブリッド給食」を提案しています。高齢者施設の場合、人員が集まりにくい早朝は小鉢を一部クックチル商品に置き換えるというのも良いかもしれません。保育園やこども園では、利用者が少ない土曜日は一部既製品を使用するというのも一つの方法です。
▶ページ内 施設向けサービス「ハイブリッド給食のご案内」を見に行く。
3.長引く物価高への対策を!
値上げをせずに満足できる給食提供へ
食材や光熱費の値上げは、給食を提供する教育機関や介護施設の方々の頭を悩ませる、大きな問題です。限られた予算のなかで栄養バランスが良い給食を提供できるよう努力をされている一方で、厳しい現実に直面している施設様も少なくありません。
名阪食品では、物価高への対策として「加工食材を使わない」「原材料から作成」「作業動線の見直し」などを行っています。その結果、物価高が進む昨今でも値上げをせずに、これまで以上に満足していただける給食を提供しています。今後もみなさまをサポートできるよう対策を講じていますので、お悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
無料資料ダウンロード

献立写真集の資料を
ダウンロードいただけます
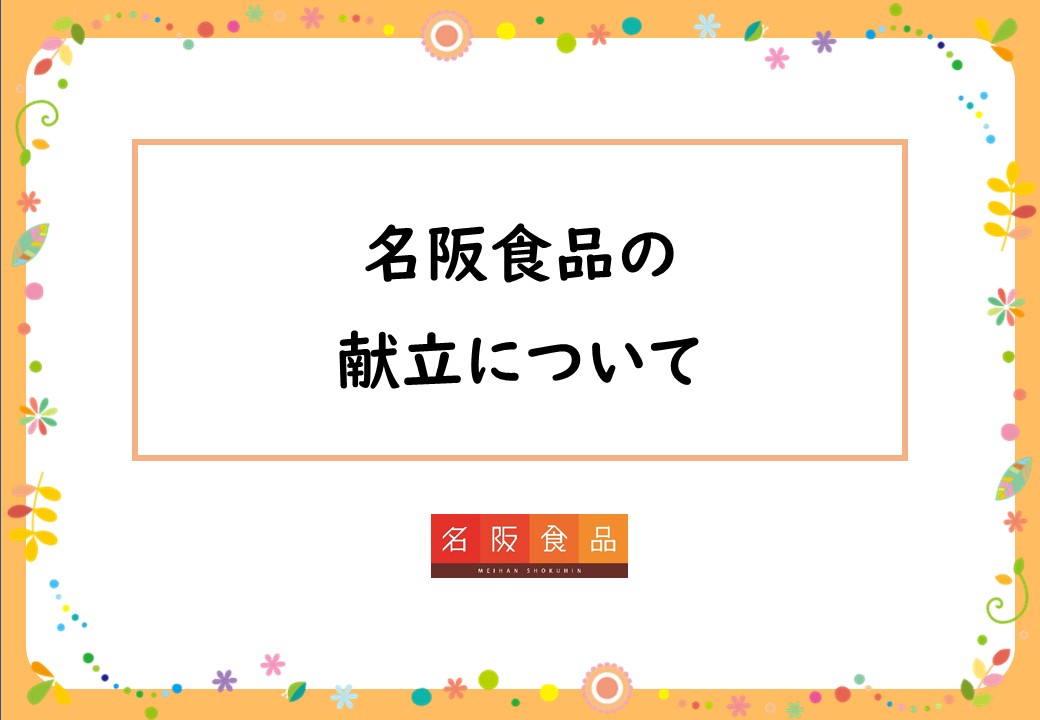
名阪食品の献立についての資料を
ダウンロードいただけます
無料資料ダウンロード
【出典】
※1総務省「2020年基準 消費者物価指数」
https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf
※2帝国データバンク「「食品主要 105 社」価格改定動向調査(9 月)」
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p220901.pdf








