高齢者が楽しめる食育レクリエーション6選!楽しみながら低栄養を防ごう

人は一生に約9万回の食事を摂ると言われており、その一つひとつの積み重ねが、生涯の健康をつくると考えられています。そのため、食に対する知識を身に付け、毎日の食生活へと反映していく力が大切です。
こうした力を育むのが「食育」であり、近年は子どもから大人まで、各年代に応じた知識のアップデートが重要視されています。そこでこの記事では、高齢者への食育レクリエーション事例や、食育が求められる背景などについてくわしく紹介していきます。
※また合わせて、サイト内におきまして「高齢者施設 お悩み解決」に関する記載もご用意しております。是非ご参考下さい。
この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム
名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。
編集方針はこちら
1.高齢者と楽しめる!
食育レクリエーション事例6選
「加齢により食欲がわきにくい」など、高齢者は食事への興味が薄れやすいと言われています。そこでおすすめしたいのが、楽しみながら食への興味を高められる、食育レクリエーションです。まずは、どのようなレクリエーションがあるのか、具体的に見ていきましょう。
①楽しみながら食を学ぶ「献立ゲーム」
「献立ゲーム」は、何人かでグループを作り、一日の献立を考えていく食育レクリエーションです。食生活に関する冊子などを用意すれば、高齢者に必要なエネルギー量や栄養素、食事の摂り方についても楽しく学べるでしょう。
②身体の仕組みについて知る「健康教室」
高齢者に起こりやすい健康トラブルに焦点を当てた「健康教室」もおすすめです。たとえば、高齢者が悩みがちなお腹の不調に注目しながら、腸の働きや消化吸収の仕組みについて教室を開いても良いでしょう。自身の身体の働きに興味がわき、食への意識を高めることが期待できます。
③地域ならでは食材で楽しむ「郷土料理を味わう会」
地域ならではの食事を皆で楽しむのが「郷土料理を味わう会」です。食べることへの興味が失われやすい、一人暮らしの高齢者が多いときにおすすめの食育レクリエーションと言えます。郷土料理はもちろん、柏餅などの季節料理を一緒に作ってみても、食への意識が高まりやすいでしょう。
④健康的な食への意識を高める「管理栄養士のランチミーティング」
身近な場所に管理栄養士がいる場合には、プロが考案したヘルシーランチを楽しみながら、食への学びを深める「管理栄養士のランチミーティング」を開催してみてはいかがですか? 食事とあわせて、健康的な食生活のポイントも話してもらうと学びも深まりやすいでしょう。
⑤ゲームで食への意識をアップ「野菜クイズ」
「野菜クイズ」は、野菜にまつわるさまざまなクイズを出題していく食育レクリエーションです。「カレーの甘みとコクを増加させる野菜は?」「キュウリについている白い粉は何?」といった身近な野菜のクイズから、食に興味を持ってもらいましょう。
⑥美味しくて楽しいから学びたくなる「食育ワーク」
食育×ウォーキング、食育×農業など、食育を別の切り口と掛け合わせて楽しむのが「食育ワーク」です。ウォーキングで食事処に向かい健康的な献立を学んだり、自分が収穫した作物を食べたりとアクティブに食への意識を高めていきます。身体を動かすので、運動不足の解消も期待できる食育レクリエーションと言えるでしょう。
2.高齢者への食育が重視される理由
高齢者への食育は、健康寿命を延ばすために重要な活動です。ここからは、高齢者への食育が重視されている理由について見ていきましょう。
(1)健康的な食事への意識が高い高齢者は多い
農林水産省の「食育に関する意識調査」によると、高齢者は健康的な食生活を心掛けている方が多い傾向にあり(※1)、20代から30代の若い世代に比べて栄養バランスを考えた食事を摂る方も増えている(※2)という結果が出ています。また、厚生労働省「国民健康・栄養調査結果の概要」によると、持ち帰り総菜・弁当を利用する割合も男女ともに60代以降は減少し、健康的な食事への意識が高い傾向(※3)にあります。
その一方で、年齢を重ねるほど栄養状態が悪い、いわゆる「低栄養」の高齢者は増加傾向です。食への興味・関心が高いにもかかわらず、なぜこうした状態になりやすいのでしょうか。
(2)高齢者に「低栄養」が多い理由とは
高齢者が低栄養になりやすい原因の一つが「孤食」だといわれています。
食事を摂るのが自分だけとなると栄養バランスが偏りやすくなるため、低栄養が生じやすいと言われています。「一人で食べると食欲がわかない」という声も多く、食事量も減りがちになるようです。
年齢を重ねると起こりやすい、唾液の分泌量の減少や入れ歯の不一致なども低栄養のリスクを高める要因と言われています。また、足腰が弱ることで買い物に行きにくくなり、口にできる食材が限られやすい方も、低栄養となりやすいでしょう。
(3)「低栄養」を防ぐためにも食育は重要!
高齢者のなかには、健康的な食事への意識にもかかわらず、身体的・環境的な要因で低栄養となってしまう方が少なくありません。こうした事態を解消するためにも、高齢者への食育は重要と言えるでしょう。
食育を通して、加齢による身体の変化やそれにともなう食生活が学べれば、健康維持に役立てることができます。また、食育レクリエーションなどをきっかけに、さまざまな交流が生まれれば孤食の割合を減らすことにもつながるかもしれません。
年齢や生活スタイルに合わせた食事方法を身に付けるサポートをすることで、身近な高齢者の方の健康を支えてみてはいかがでしょうか。
3.食育で高齢者の健康寿命を延ばす!
高齢者施設では給食の充実も重要
食事をするという行為は、身体的な健康だけでなく、気持ちにも大きな影響を与えるものです。「美味しい」「楽しい」といった満たされた気持ちは、高齢期の日常生活を支える基盤にもなるでしょう。
こうした食事の楽しさに加えて、年代に合わせた知識のアップデートができれば、高齢者の健康寿命を延ばすことにもつながります。ぜひ、高齢者施設などで今回紹介した食育レクリエーションを行ってみてはいかがでしょうか。
また、高齢者施設内の給食を充実させることも、食育の一環といえます。栄養バランスのとれた給食を日頃から口にしてもらうことで、高齢者の方に健康的な食生活を提供していきましょう。
無料資料ダウンロード

献立写真集の資料を
ダウンロードいただけます
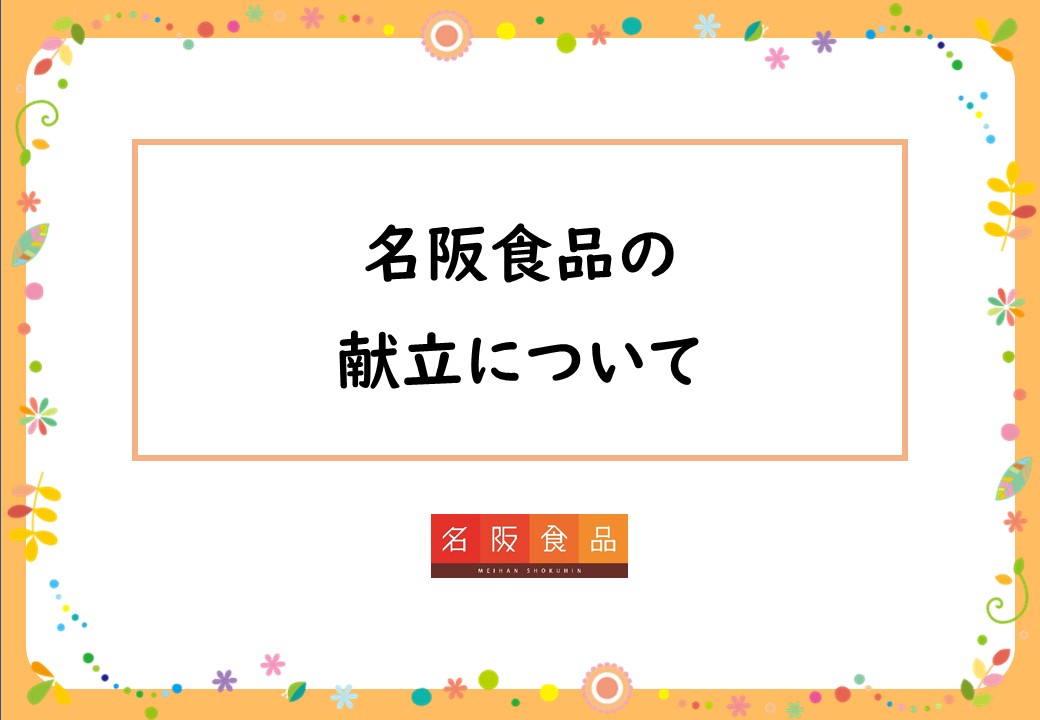
名阪食品の献立についての資料を
ダウンロードいただけます
無料資料ダウンロード
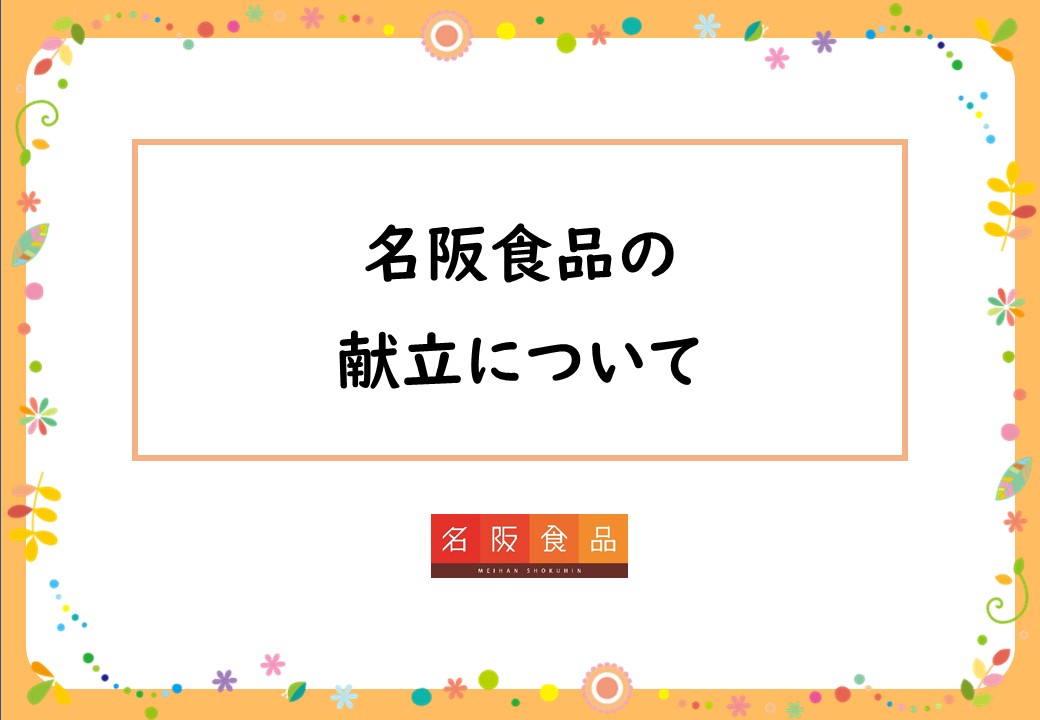
名阪食品の献立についての資料を
ダウンロードいただけます

食育実施例集の資料を
ダウンロードいただけます
【出典】
※1農林水産省「食育に関する意識調査報告書(令和4年3月)」
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki/r04/zuhyou/z2-1.html
※2農林水産省「食育に関する意識調査報告書(令和4年3月)」
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki/r04/zuhyou/z2-2.html
※3厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf
※4農林水産省「食育に関する意識調査報告書(令和2年3月)」
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki/r02/zuhyou/z3-1.html





