介護施設のBCP策定義務化|作成手順やポイント、成功事例をご紹介

2024年1月1日に発生した能登半島地震により、犠牲となられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、被災されたすべての方々にお見舞い申し上げます。
災害に際して、介護事業では医療機関と同じように人々の安全を守り、事業を継続すること、そして施設や設備の早期復旧が求められることになるでしょう。実際、すべての介護施設においては、危機発生時に備えた「事業継続計画(BCP)」を2024年4月までに策定することが義務付けられています。
そこでこの記事では、これからBCPの策定や更新をする介護事業者様に向けて、実際の手順や作成するうえでのポイントについて解説します。成功事例もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
※また合わせて、サイト内におきまして「幼保育園 お悩み解決」「特養・老健 お悩み解決」「社員食堂・寮 お悩み解決」に関する記載もご用意しております。是非ご参考になさって下さい。
▶サイト内 お悩み解決「こども園・保育園・幼稚園」ページを見に行く。
▶サイト内 お悩み解決「特養・老健」ページを見に行く。
▶サイト内 お悩み解決「社員食堂・寮」ページを見に行く。
この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム
名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。
編集方針はこちら
1.介護事業者のBCP策定の義務化について
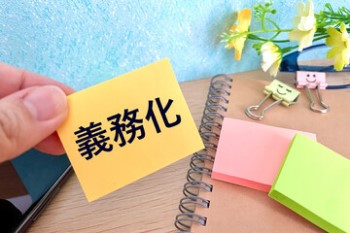 介護事業は、医療と同様、有事のときこそ継続が求められる事業です。2021年の介護報酬改定で、すべての介護施設において2024年4月までに「事業継続計画(BCP)の策定」が義務化されることが決定しました。
介護事業は、医療と同様、有事のときこそ継続が求められる事業です。2021年の介護報酬改定で、すべての介護施設において2024年4月までに「事業継続計画(BCP)の策定」が義務化されることが決定しました。
BCPは「Business Continuity Plan」の略称で、事業継続計画と訳され、企業が自然災害または取引先の倒産などの経営困難な状況においても、重要業務が継続できるようにまとめた方策を指します。義務化に従わず、BCPを策定しない事業者は、介護報酬の減算となるケースがあります。また、該当の介護施設にいる入居者・職員に被害があった場合、安全配慮義務違反に問われることになってしまうのです。
2.BCP策定の手順とポイント
介護事業者におけるBCPの作成にあたっては、厚生労働省から作成を支援するため、ひな形が公開されています(※1)。有事発生時の業務継続ガイドラインとともに、入所系・通所系・訪問系の3パターンのひな形などが閲覧可能です。
BCPを作成する際には、ひな形に必要事項を記入していく方法がスムーズでしょう。ここでは、感染症(新型コロナウイルス感染症)と、自然災害のひな形を使った、作成手順とポイントをご紹介します。
(1)感染症発生時におけるBCP策定について
 厚生労働省の該当ページに、各種資料と作成手順の研修動画が掲載されています。閲覧できる感染症に関するガイドライン資料は下記の通りです。
厚生労働省の該当ページに、各種資料と作成手順の研修動画が掲載されています。閲覧できる感染症に関するガイドライン資料は下記の通りです。
- 新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン
- 感染症ひな形(入所系・通所系・訪問系の3パターン)
- 例示入りのひな形(令和3年度:入所系・通所系・訪問系の3パターン)
- 様式ツール集
該当する業態のひな形、様式ツール集のファイルをダウンロードして、BCP作成を進めましょう。
>>ひな形のダウンロードはこちらから
- 施設内の情報共有ルール・役割分担を決める ・感染者が出た場合の、各業務における担当者を決定する(誰が、何をするかにも留意) ・関係者の連絡先および連絡フローの整理
- 感染発生時の対応をシミュレーションする ・感染者が発生した場合でも各種サービスが継続されるようにシミュレーションを行う
- 職員不足に備えて人員確保をしておく
- 業務の優先順位を整理する ・様式ツール集のなかには、職員の出勤率に合わせた業務対応フォーマットあり
- 感染症発生時に行動できるよう、周知・研修・訓練を行う ・最新の知見を取り入れ、定期的に見直すことも重要
(2)自然災害発生時におけるBCP策定について
 厚生労働省の該当ページで閲覧できる、自然災害に関するガイドライン資料は下記の通りです。
厚生労働省の該当ページで閲覧できる、自然災害に関するガイドライン資料は下記の通りです。
- 自然災害発生時の業務継続ガイドライン
- 自然災害ひな形
- 例示入りのひな形(令和3年度:共通・サービス固有の2パターン)
<自然災害発生時のBCP作成手順とポイント>
該当するひな形のファイルをダウンロードして、BCP作成を進めましょう。
>>ひな形のダウンロードはこちらから
- 施設内の情報共有ルール・役割分担を決める ・感染者が出た場合の、各業務における担当者を決定する(誰が、何をするかにも留意) ・関係者の連絡先および連絡フローの整理
- 感染発生時の対応をシミュレーションする ・感染者が発生した場合でも各種サービスが継続されるようにシミュレーションを行う
- 職員不足に備えて人員確保をしておく
- 業務の優先順位を整理する ・様式ツール集のなかには、職員の出勤率に合わせた業務対応フォーマットあり
- 感染症発生時に行動できるよう、周知・研修・訓練を行う ・最新の知見を取り入れ、定期的に見直すことも重要
3.地震時のBCP対策成功事例
これまでにBCP策定が行われていたことによって、事業の継続や早期復旧に成功した事例は多くあります。実効性のあるBCP対策として、成功事例を3つご紹介します。
(1)迅速な状況把握で震災5ヶ月後に完全復旧を実現
 2016の熊本地震では、マグニチュード6.5の地震が起きました。熊本県内で自動車を製造する、ある自動車メーカーのグループ会社の事業所でも、全般に大きな被害を受け、震災の翌日より生産がストップしました。
2016の熊本地震では、マグニチュード6.5の地震が起きました。熊本県内で自動車を製造する、ある自動車メーカーのグループ会社の事業所でも、全般に大きな被害を受け、震災の翌日より生産がストップしました。
しかし、グループ会社において「BCPポリシー」を策定しており、それに基づき生産ラインの復旧や被害の状況把握が迅速に行われたおかげで、震災発生から約5ヶ月後には完全復旧に至ったそうです。事前に事業所の耐震工事を完了していたことで工場設備のダメージを最小限に抑えられたこと、災害備蓄品を準備していたことなどが役立ったと言われています。
(2)量産工場を複数準備する「マルチハブ化」などで災害に対処
 半導体を製造するある企業では東日本大震災発生時、工場が3ヶ月間ストップする事態が発生。この経験を教訓に、企業のBCP策定を見直したそうです。 見直されたのは、大きく2点。1つ目は、各工場において震度6強の地震に耐えられる、耐震性強化工事を進めたこと。2つ目は、量産工場を2ヶ所以上準備する「マルチハブ化」に取り組んだことです。特にマルチハブ化によって、万が一工場の操業が停止した場合も別工場で同じ製品や部品を製造できる体制が確立され、生産工程への影響を最小限にとどめられるようになりました。 これらのBCP策定の見直しによって熊本地震発生時には早い段階での生産再開が実現しました。
半導体を製造するある企業では東日本大震災発生時、工場が3ヶ月間ストップする事態が発生。この経験を教訓に、企業のBCP策定を見直したそうです。 見直されたのは、大きく2点。1つ目は、各工場において震度6強の地震に耐えられる、耐震性強化工事を進めたこと。2つ目は、量産工場を2ヶ所以上準備する「マルチハブ化」に取り組んだことです。特にマルチハブ化によって、万が一工場の操業が停止した場合も別工場で同じ製品や部品を製造できる体制が確立され、生産工程への影響を最小限にとどめられるようになりました。 これらのBCP策定の見直しによって熊本地震発生時には早い段階での生産再開が実現しました。
(3)細かな内容確認と更新で実効性を維持
 障がい者施設・保育所などの事業を行うある社会福祉法人では、きめ細かな事業継続計画書を作成していることが大きく評価されています。基本計画以外にも、地震・感染症・風水害などのケースごとにBCPが作られており、被害想定や初動対応について詳しく規定。また、運営するすべての事業所・施設における備蓄品の数量、職員数、連絡先も記載されています。
障がい者施設・保育所などの事業を行うある社会福祉法人では、きめ細かな事業継続計画書を作成していることが大きく評価されています。基本計画以外にも、地震・感染症・風水害などのケースごとにBCPが作られており、被害想定や初動対応について詳しく規定。また、運営するすべての事業所・施設における備蓄品の数量、職員数、連絡先も記載されています。
また、このBCP策定においては実効性を維持するために、各項目に「毎年4月1日に調査を行う」ことが記されており、内容確認と更新ルールが決められているのも特徴です。
4.作成時は同業種・同規模のBCP策定を参考に
ここまで、BCP策定の手順やポイント、成功事例などをご紹介しました。企業がBCPを作成することは、危機発生時に限らず、平時にも好影響をもたらす経営施策にもなり得るでしょう。
実際にBCP策定を進める際は、自社と同業種、似た規模の事業におけるBCP策定内容を参考にしてみてください。災害時に、迅速な初動対応、復旧が行えるようにするためにも、施設運営者はBCPの策定・更新を進めていきましょう。
【出典】
※1 厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修資料・動画」
※2 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」
無料資料ダウンロード

献立写真集の資料を
ダウンロードいただけます
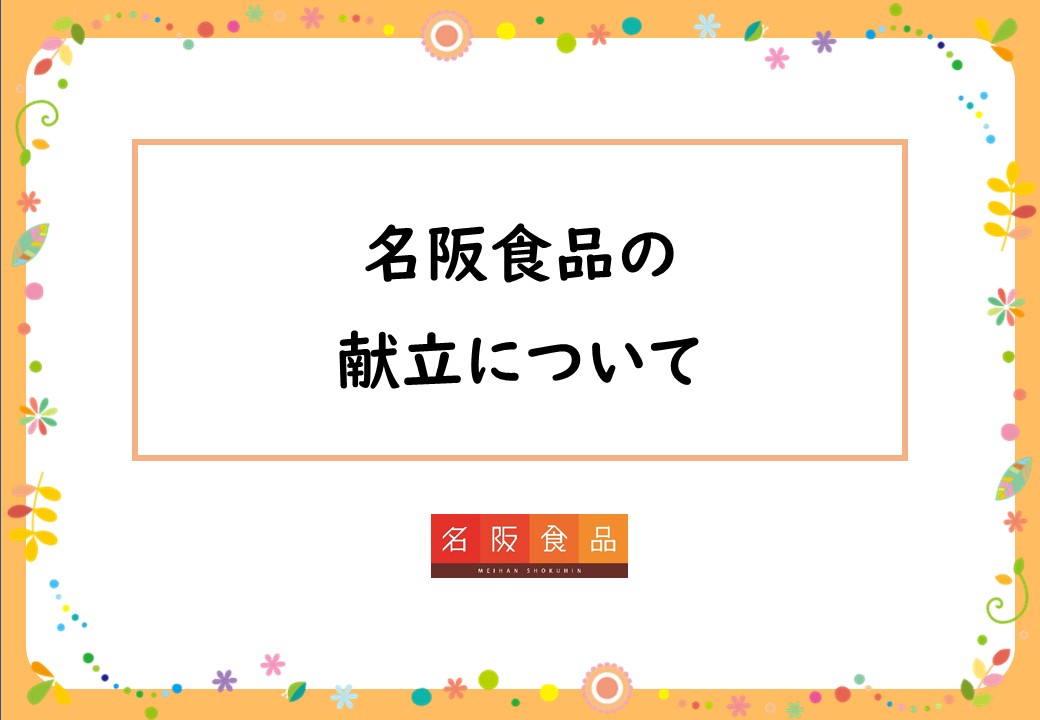
名阪食品の献立についての資料を
ダウンロードいただけます
無料資料ダウンロード
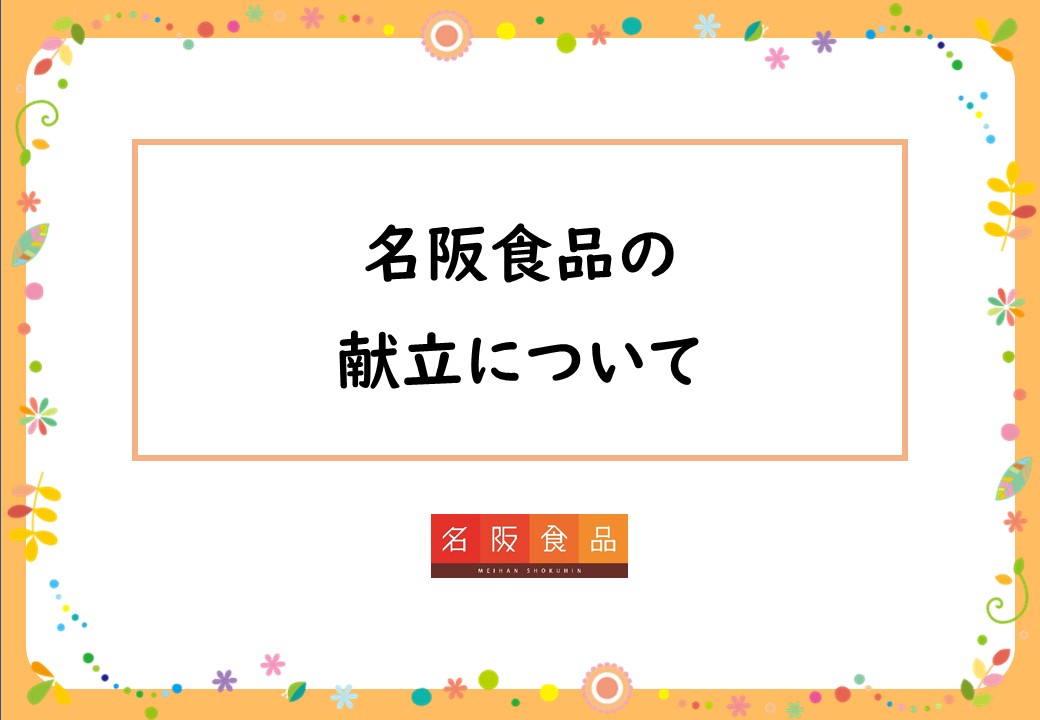
名阪食品の献立についての資料を
ダウンロードいただけます

食育実施例集の資料を
ダウンロードいただけます





