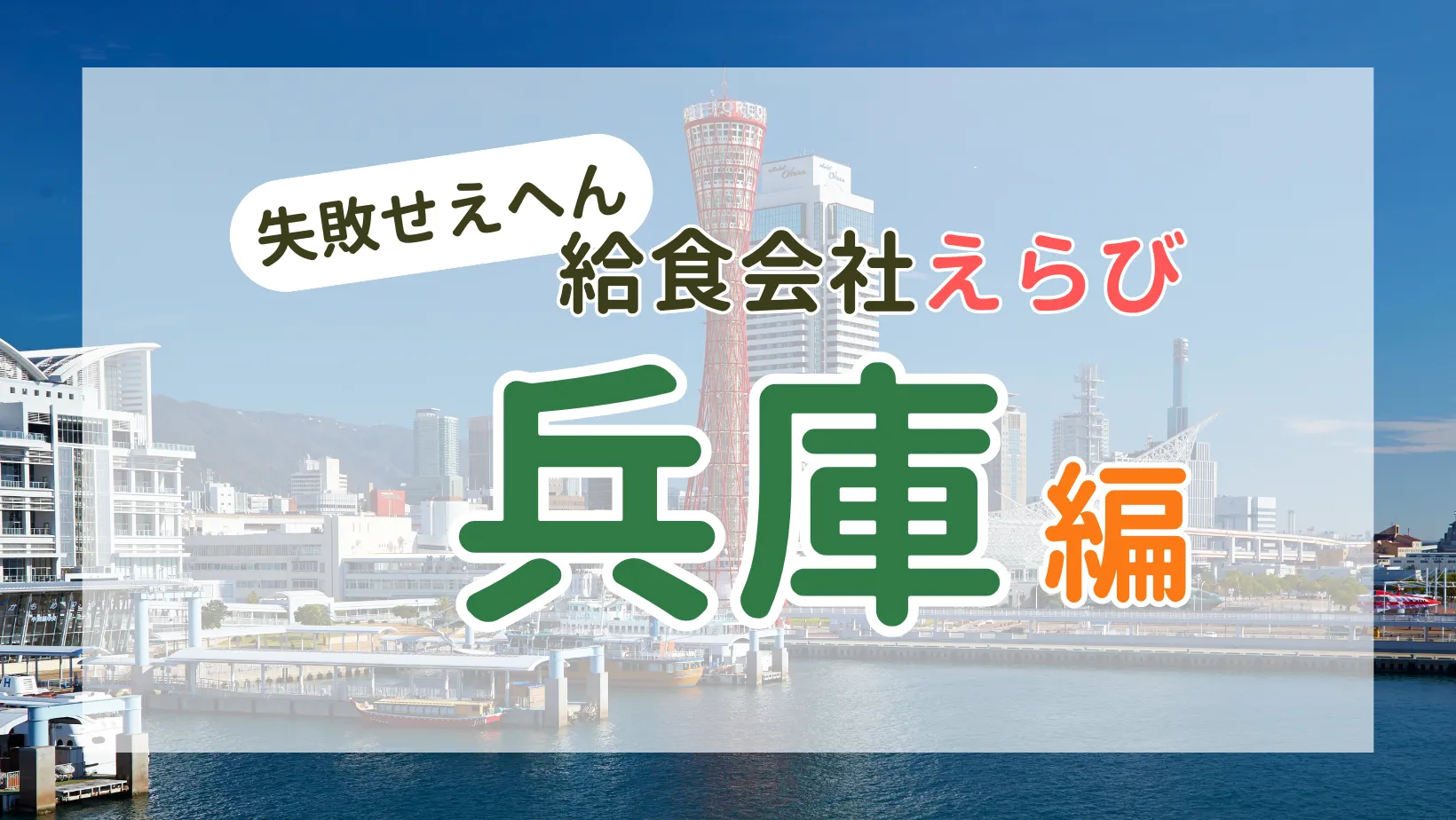食中毒は梅雨時期から気をつけよう!春夏の食中毒の原因や給食会社の対策を解説

食中毒は、年間を通して発生が報告されていますが(※1)、特に梅雨時期から発生件数が増加する傾向にあります。給食を提供する施設では、梅雨入り前から食中毒への知識を深め対策をとる必要があるでしょう。
そこで今回は、春夏に多い食中毒の特徴や気をつけるべき菌や、ウイルスについて解説、そして給食会社(当社)の食中毒防止の取り組みについても触れていきます。
※1出典:厚生労働省「食中毒統計資料」(令和3年)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html
この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム
名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。
編集方針はこちら
1.春夏に多い食中毒の特徴
意外と知られていませんが、寒さが和らいで気温が上昇しはじめる春も食中毒への注意が必要な季節です。春は通年発生するアニサキスという寄生虫が原因の食中毒が最も多く、次いでノロウイルスなどによるウイルス性の食中毒が冬から春にかけて引き続き発生しています。また、ほかの季節に比べ、野草・キノコ・フグなどの自然毒が原因物質となった食中毒が見られるのも特徴でしょう。
夏場は、食中毒全体のうち7~9割ほどを占める細菌性の食中毒が1年を通して最も増える季節です。食中毒の原因となる細菌は多くの場合、約20℃の室温から活発に増殖をはじめ、37~40℃をピークに食材や食品内で繁殖していきます。したがって夏は、細菌にとって最適な環境と言えるのです。さらに細菌は、高温多湿を好む傾向にあるため、本格的に夏に入る前の梅雨時期から食中毒に気をつける必要があります。給食の提供を行う施設でも、手洗いや食材の保存方法、加熱処理など食中毒予防のための対策が適切に行われているかどうか再確認するといいでしょう。
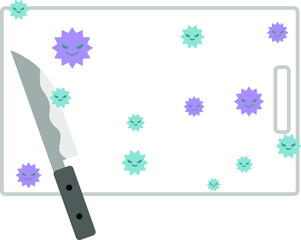
2.春夏に多い食中毒には何がある?
気をつけるべき菌やウイルスを紹介
続いて、春夏に気をつけるべき菌やウイルスを紹介していきます。
(1)感染力が高い「ノロウイルス」
ノロウイルスは、食品・手指を介して口から体内に入ることで感染します。腸内で増殖し、下痢や嘔吐、腹痛などを引き起こすウイルスです。感染力の強さから、集団感染のリスクが高いとされています。考えられる感染様式は、汚染された二枚貝を生や加熱不十分で食べた場合や汚染状態にある井戸水・簡易水道を消毒不十分で飲んだ場合などです。
また近年では、食品取扱者が感染し、調理などでその者を介した食品が原因となる感染事例が多く見られています。ノロウイルス感染者は、人によっては軽症または無症状の場合もあり、気づかず食材を二次汚染して食中毒につながってしまうこともあるので、十分な注意が必要です。
(2)加熱不良で食中毒に発展「カンピロバクター・ジェジュニ/コリ」
カンピロバクター・ジェジュニ/コリを原因とする食中毒は、近年国内で報告されている細菌性食中毒のなかで最も多い発生件数です。わずかな菌数で発症するとされており、生の状態や加熱が不十分な食品を提供した場合に、食中毒事故につながりやすいとされています。
多くの場合、患者は1週間ほどで完治しますが、抵抗力の弱い方や乳幼児、高齢者などは重症化する恐れがあるため注意が必要です。加えて感染から数週間経過した頃に、呼吸困難や手足の麻痺、顔面神経麻痺などが起こる「ギラン・バレー症候群」を発症するケースも指摘されています。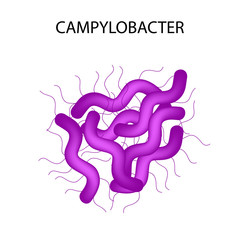
(3)大量調理などのつくり置きに注意「ウエルシュ菌」
ウエルシュ菌により発生する食中毒は、別名「給食病」と呼ばれています。カレーなどの大鍋で調理する煮込み料理を大量につくり置きし、放置していたことが原因となるケースが多いようです。100℃で1時間加熱しても死滅しない強い芽胞をつくる特徴があり、一般的な加熱では対処できません。
しかし、食中毒発症には多くの菌量が必要とされています。そのため温め直しによる再加熱や調理後の速やかな喫食、適切な温度管理下での小分け保存などが感染防止に最も有効的です。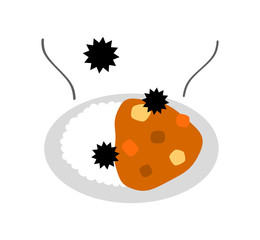
3.給食会社(当社)の食中毒防止の取り組みについて
委託給食サービスを行う名阪食品では、食中毒防止のための衛生管理を徹底しています。そのうえで、食中毒が発生した場合に被害を最小限にとどめる危機管理体制も万全に備えています。
ここでは、名阪食品が実践する食中毒防止の取り組みをお伝えしていきましょう。
(1)仕入部による取り組み
名阪食品の仕入部では、近畿地区をメインに食品メーカーや卸などから食材の一括納入を行っています。その際に実施される、配送記録および適温配送も食中毒防止の取り組みの一環です。加えて納品時には、消味期限や品質に対し厳重な注意を払い、検収を行っていますので、賞味期限切れや傷んだ食材が受け入れられることもありません。
もしも食材に異物混入をはじめとした不備が見つかった場合には、調理員が担当栄養士を通じて仕入部に報告することを定めています。さらに仕入部から納入元へ連絡を取り、報告書の提出を要請するといった方法で、全体での改善を図る体制を整備しています。
(2)管理担当者の取り組み
管理担当者は、エリアごとの常時巡回を実施し、調理業務・衛生管理・接客サービスが適切に行われているかをチェックしています。そして調理スタッフが食中毒防止を含む業務への意識を高く維持できるよう、現場運営のサポートを実施。
管理担当者による社内研修にも力を入れています。従業員入社時には、衛生管理のルールや手洗いの方法、体調管理などをマニュアル化したものを用いて個別・現場単位で研修を行います。さらに調理員へ毎月の提出を課している「成長フォローシート」の情報を元にした面談も管理担当者の業務のひとつです。衛生管理を現場だけに任せず、実施の漏れを防ぐ管理体制を敷いています。
(3)衛生管理室・担当栄養士の取り組み
名阪食品では、衛生管理室(C&SS室)を独自に設置し食材の納入をはじめ調理や食事提供、清掃に至るまで衛生管理の項目をトータルに教育指導しています。衛生管理マニュアルの作成や年3回の衛生講習、定期的な手洗いチェッカー・検査薬を用いた衛生点検により食中毒発生防止を図っています。
担当栄養士は、衛生的な食材の取り扱いができるよう留意しながら、季節に合わせて献立を作成。夏季は、スライスハム・鶏ミンチ・釜揚げしらすなどの食材や、白和え・手づくりハンバーグといった料理の調理を規制し、食中毒発生のリスクの低減に努めています。
4.食中毒が多い春夏。
安心できる給食委託会社を選びましょう
夏に多いイメージのある食中毒ですが、気温が上がり始める春や湿度の高い梅雨時期から警戒が必要であることがわかりました。給食提供においては、適切な衛生管理が食中毒発生防止の鍵となってくるでしょう。給食の外部委託を検討される場合には、徹底した衛生管理の実施や管理体制に注目し、安心できる給食委託会社を選定してくださいね。
無料資料ダウンロード

献立写真集の資料を
ダウンロードいただけます
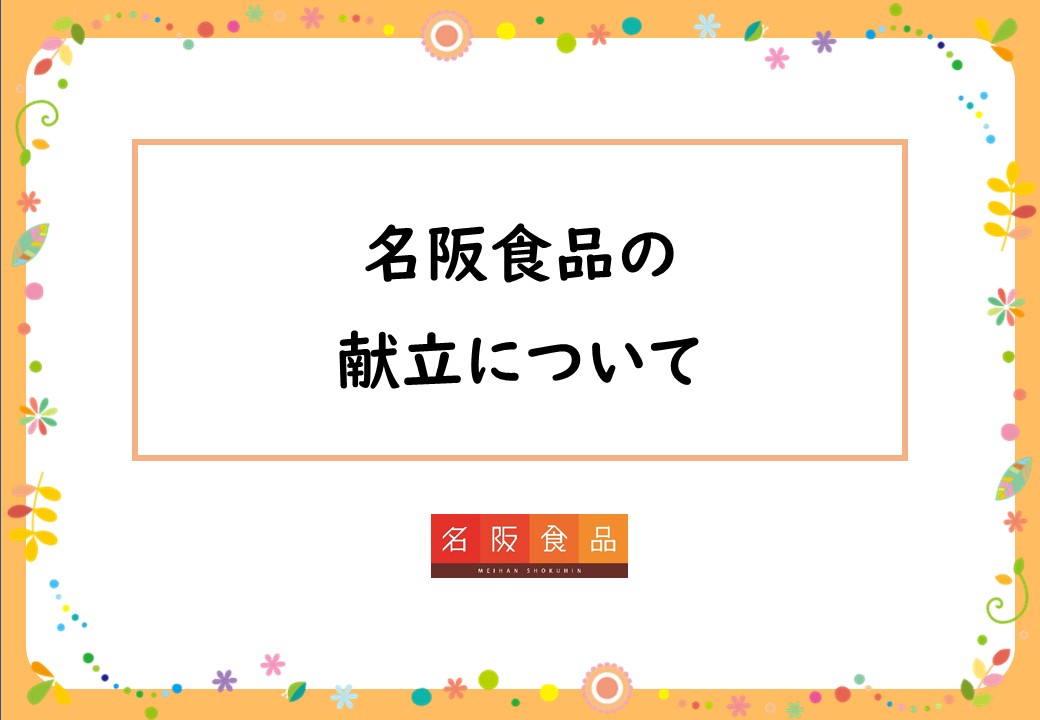
名阪食品の献立についての資料を
ダウンロードいただけます
無料資料ダウンロード
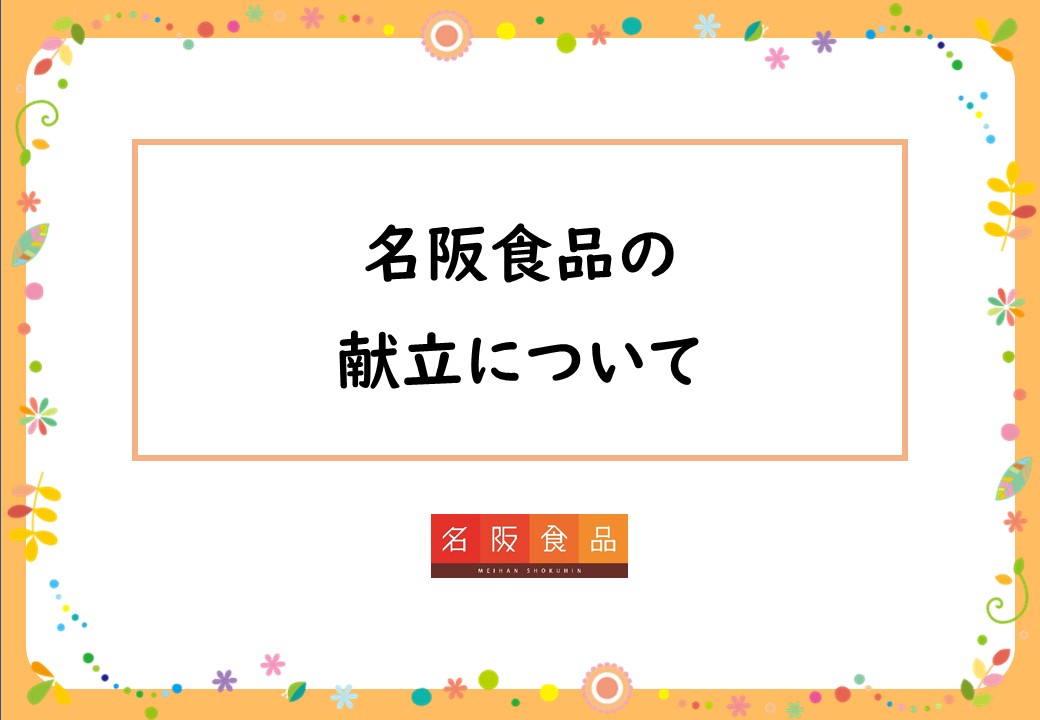
名阪食品の献立についての資料を
ダウンロードいただけます

食育実施例集の資料を
ダウンロードいただけます
【出典】
※1出典:厚生労働省「食中毒統計資料」(令和3年)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html