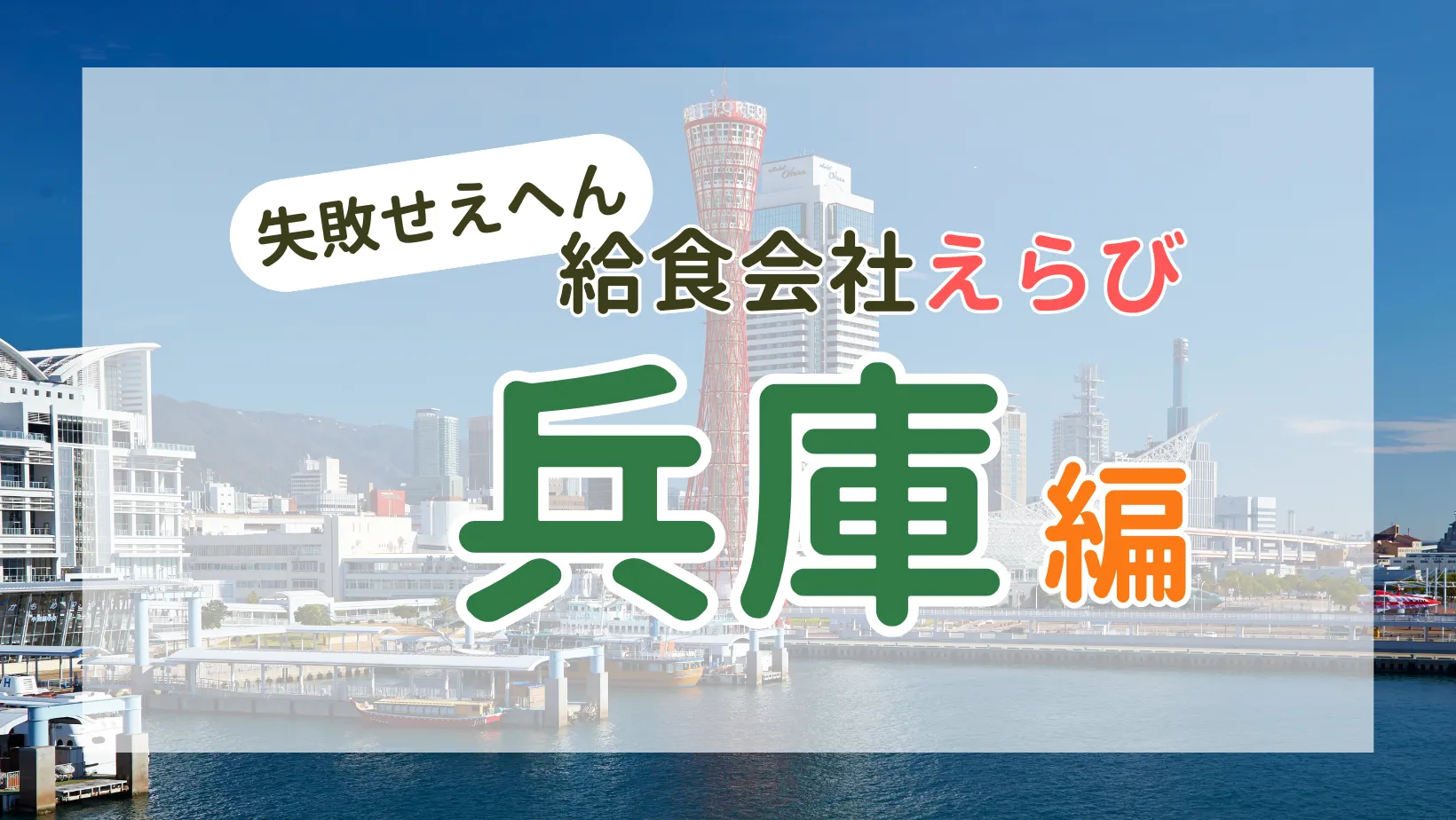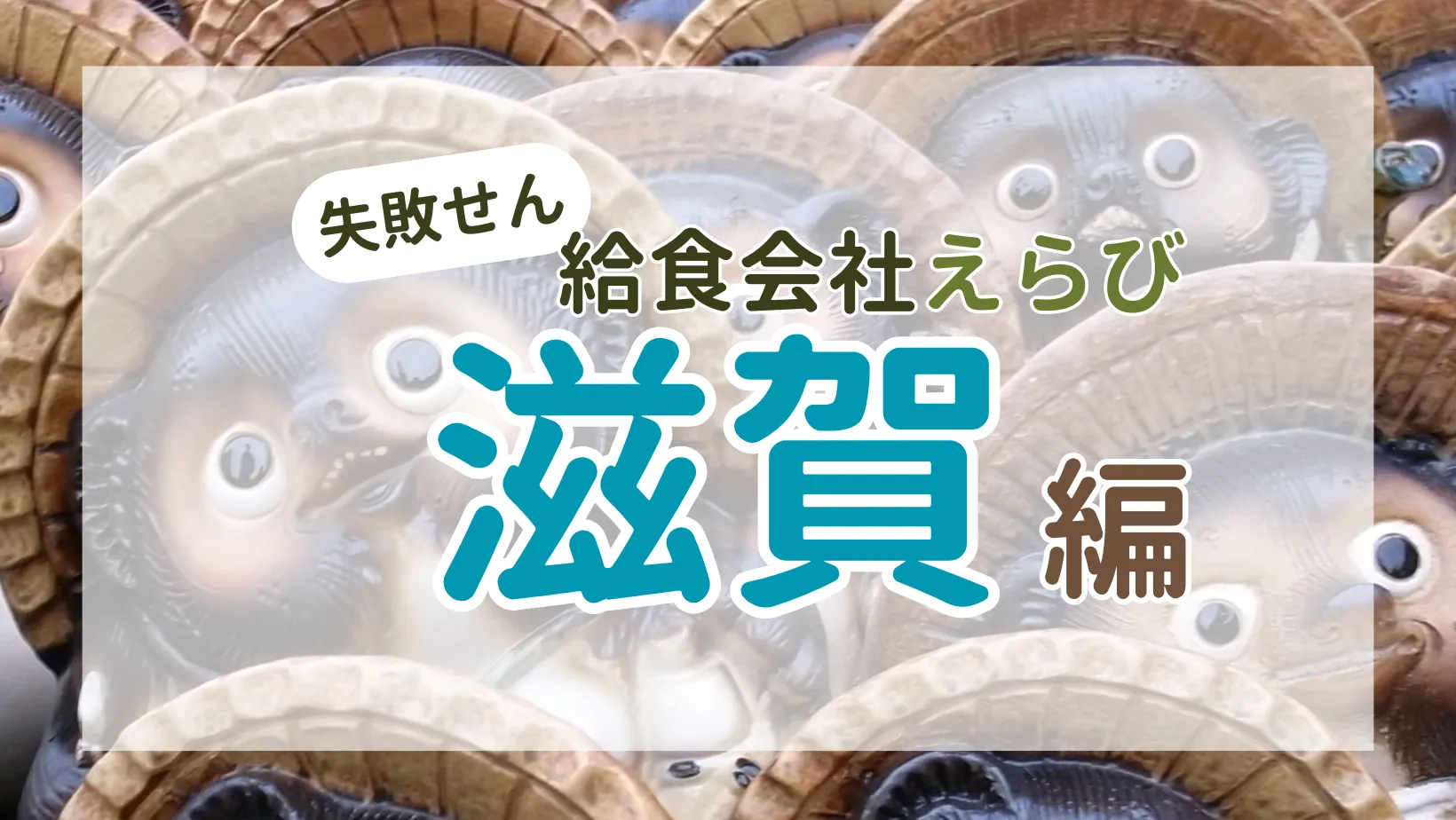入園児に多いアレルギーとは?幼稚園・保育園で気を付けたいアレルギーのこと

幼幼稚園や保育園で提供される給食は、美味しさや栄養バランス、衛生面などはもちろん、アレルギー食に対応しているかどうかも注目すべきポイントです。
食物アレルギーをおもちの園児様にも対応した給食を提供しているということであれば、保護者様も安心できるでしょう。
そこで今回は、園児様の入園時に行うべきアレルギーの確認および対応の流れをご紹介します。
併せて、園児様に多い食べ物のアレルギーや給食会社の対応についてもお伝えしていきます。
この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム
名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。
編集方針はこちら
1.入園時のアレルギー確認・対応の流れ
まずは、入園時に必要なアレルギー確認と対応の流れを解説していきます。
(1)医療機関の受診
食事後にアレルギー症状が出た経験のある園児様は、入園前にアレルギー専門医がいる医療機関を受診し、アレルギー症状の有無や程度を確認してもらう必要があります。
食物アレルギーの正確な診断を受けるためにも、血液検査だけでなく経口負荷試験を受けてもらうことが望ましいです。
また、園でのアレルギー対応は、除去が必要な食べ物とその理由、緊急時の対応などが記載された「生活管理指導表」に基づき行います。入園前には、医療機関の確実な受診と生活管理指導表の提出を保護者様にお願いしましょう。
(2)入園前、入園直後の面談(話し合い)
給食の提供が始まる前に、保護者様と園でアレルギー対応について話し合いの場を設けます。園長・主任・担任・栄養士(自園調理の場合)など、可能な限り多くの職員が出席し、担任が不在の場合でも対応できるように園全体で情報共有しましょう。
アレルギーのある食材が給食で使われる場合、代替メニューでの提供や、代わりのおかずを家庭で用意するなどの対応がなされます。
対応方法は、園児様の食物アレルギーの重症度や、アレルゲンとなる食品の種類、園の状況によっても異なります。
具体的な対応方法を保護者様へ説明できるようにしておくとよいでしょう。

(3)緊急時の対応についての話し合いと訓練の実施
誤食やアレルギー症状が発生した緊急時には、生活管理指導表をもとに抗ヒスタミン薬の飲み薬や、エピペン®︎を使った対応が求められる場合があります。医療機関から薬が処方されている園児様の場合は、必要に応じてご家庭から薬を預かっておきましょう。
薬の保管方法や緊急時の対応などは、保護者様から主治医へ確認してもらい、その情報をもとに保護者様と園でよく相談しておきます。
また、いざというときに冷静に対処できるように、「エピペン®講習会」を実施し、訓練しておくことも大切です。
全職員が、適切にエピペン®を取り扱えるようにしておくことが望ましいでしょう。

2.園児様に多いアレルギーとは
ここでは、園児様に多くみられる食物アレルギーを紹介していきます。
(1)卵(鶏卵)アレルギー
主に卵白が原因で起こる卵アレルギーは、新生児から年長くらいの子どもに多く見られます。
この頃の子どもは消化器が未熟であるため、抗原が腸の粘膜を通りやすく、
卵白に異常に反応してしまう場合があるのです。
卵アレルギーの症状は、軽ければ半日から数日じんましんが少し出る程度で早めに消えていきます。
しかし強いアレルギー反応が起きた場合は、すぐに頬が赤くなったり、口まわりが赤くなったり、最悪のケースでは呼吸困難になることもあります。
市販の食べ物には、原材料や加工の過程で卵が使われていることもあるため、パスタ・ケーキ・ラーメン・コンソメスープなどに注意しましょう。
また豚肉のミンチなど、製造の際に卵の処理を行うものと同じ製造工程で作られる食品にも、気をつける必要があります。
(2)牛乳アレルギー
牛乳アレルギーは、食物アレルギーのなかで卵の次に多い疾患です。
アレルギーの症状には、じんましんなどの皮膚症状や咳、呼吸困難などがあります。
重症の場合には、アナフィラキシーショックが起こる恐れもあるため注意が必要です。
牛乳アレルギーで気をつけるべき食品には、牛乳はもちろん牛乳を含む加工食品があります。
ヨーグルトやチーズなどはわかりやすいですが、ハムやウインナーといった肉類の加工食品など、一見わかりにくいものにも含まれている場合があるのです。
牛乳が含まれる加工食品には、牛乳が含まれていることを表示する義務があるので、
食品を選ぶときはよく確認しましょう。
(3)小麦アレルギー
小麦アレルギーのアレルゲンは、小麦の主成分であるタンパク質のグルテンやグリアジンであり、これらが消化できないことでアレルギーが引き起こされます。
小麦アレルギーでは、じんましんや皮膚のかゆみなどの症状が見られるでしょう。小麦が使われている食品として、パン・うどん・ラーメン・パスタなどを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、ほかにも加工食品の揚げ物やスナック菓子に使われたり、食品に粘り気を出す目的で使用されたりということもあります。また、小麦アレルギーが重度の場合は、調理時に小麦の粉末が少量混入しただけでもアレルギー症状が出る恐れがあることから、調理過程を分けるなどの対策を行うとよいです。
3.給食会社の対応
多くの給食会社では、アレルギー事故を防ぐための対応マニュアルを作成し、勉強会を実施するなど、スタッフへの教育を徹底しています。アレルギーに配慮した給食の提供を開始する前には、医師からの生活管理指導表に基づき、給食会社の栄養士が園の先生、保護者様と面談を実施します。
そして面談で得た情報をもとに、献立作成時のアレルゲンの確認や対応方法の検討が行われているのです。
名阪食品では、安全確保のため、原則アレルギーの原因となる食材を完全除去で対応しています。完全除去対応には、完全除去した献立に代替食材を加える「代替食対応」と、完全除去した献立に代替を行わない「除去食対応」の二通りの対応が可能です。
もし十分な安全性が確保できないと判断される場合は、除去食対応で園内のアレルギー発症を防いでいます。アレルギー食は個別に給食室で盛り付けして、ラップや食札に対象園児様の氏名とアレルゲンを明記します。二名以上でチェックを行い、職員様へ手渡しする際にはアレルギー対応を声出しで確認。
ほかにもアレルギー食用の食器使用を提案するなど、安全に給食を提供するための工夫や取り組みを行っています。
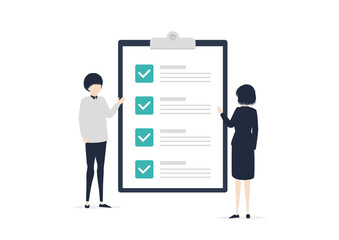
4.園児様が安心して食べられる、楽しめる給食を!
アレルギーをもつ園児様を受け入れる幼稚園や保育園は、入園前から保護者様と面談を行い、しっかりと情報収集する必要があります。そして入園後もしっかりと気を配り、園児様が毎日の給食を安心して食べられるよう取り組むことも当然求められます。特別な配慮が必要な食物アレルギーだからこそ、給食を委託する際は信頼できる会社を選ぶことが重要だと言えるでしょう。名阪食品では、園内でのアレルギー発症をなくすためにも、準備から給食の提供に至るまでさまざまな工夫と取り組みを実施しています。
どういった取り組みなのかの詳細については、ぜひ下記の資料をご覧ください。

無料資料ダウンロード

サンプル献立を
ダウンロードいただけます

こちらの導入事例資料を
ダウンロードいただけます