脱水症を予防する食事・水分補給とは?

近畿・東海地方も梅雨入りし、これから気温・湿度が上昇していきます。
季節の変わり目は、気温の変動が大きく体の準備もできていないため、
体温調節機能に異常が起きやすく要注意です。
またこの時期は、春に生活環境が大きく変わった方も多く、
環境変化に慣れないことから体調の変化に気づかずついつい熱中してしまったり、
いつも以上の緊張感により、発汗や呼吸に伴う脱水が起こります。
脱水とは?

脱水とは、体に必要な水分が不足している状態をいいます。
私たちは飲水や食事から水分をとり、
呼吸や汗により無意識のうちに水分を失ったり、
尿や便によりほぼ同じ量の水分を排泄することで
体内のバランスを保っています。
この体内に吸収する水分と排泄する水分のバランスが崩れ、
身体の水分が失われた状態のことを言います。
”かくれ脱水”に気をつけましょう!
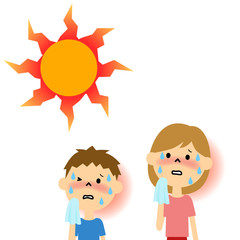
脱水症は、軽度の症状から重度の症状まで分類されていますが、
なりかけや軽度である場合、明確な自覚症状を感じにくいのが特徴です。
脱水症になりかけているのに、
本人や周囲が気づかないため、有効な対策がとれていない状態のことを
「かくれ脱水」と言われています。
特に暑い季節の屋内や就寝中、車の運転中など風通しが悪い環境に居るなど、
こまめな水分補給ができないと起こりやすいことが報告されています。
高齢者は特に注意!

脱水のリスクが高いのは高齢者です。
かくれ脱水は誰にでも起こり、水分補給によって改善します。
高齢者の場合は、脱水の初期段階であっても回復する力が弱くなっており、
脱水症にまで進みやすいと言われています。
また、心不全や高血圧などの持病がある人は、
体の外に水分を出す薬を服用しているため要注意です。
便秘で下剤を飲んでいる人も水分が排出されるため、リスクが高まります。
マスク着用中も注意!
例年に比べマスクを着用する時間が増えています。
マスク着用下では、
①マスクで熱がこもり、熱中症になりやすい
②のどの渇きを感じにくい
③マスクを外すのが面倒で水分補給の回数が減る
ということで、
かくれ脱水や脱水になる危険性が高いといわれています。
【食事で予防】"しっかり3食とる!"
通常、食事から約 1000ml の水分が摂取できます。
また食事中、食事の間で水分をこまめにとりましょう。
喉の渇きを感じる前に水分をとることも大切です。



何もしなくても身体から水分は失われます。
水分は水かお茶でとりましょう。
ジュース・清涼飲料水やお酒を水分の代わりとすることは
脱水を助長するため避けましょう。
"スポーツドリンクは発汗時だけでなくエネルギー補給にも"
水分吸収が早いという特徴があります。
運動や炎天下での作業など汗をかく場合は、水・お茶と併用しましょう。
また、水に比べてエネルギーが高く、
食欲が湧かない時に飲むとエネルギー補給の助けにもなります。
但し、スポーツドリンクや経口補水液だけの大量摂取は危険です。
多くのスポーツドリンク、経口補水液はビタミン B1を含みません。
食事をしない上に、多飲するとビタミン B1欠乏症を発症する可能性があります。
※以下の方は、医療関係者との相談が必要な場合があります。
【水分制限が必要な方】
医師から指示されている 1 日の水分量を守りましょう。
【塩分またはカリウム制限の適応がある方】
スポーツドリンクや経口補水液は電解質を補うため、
塩分やカリウムを多く含んでいます。
積極的な摂取は過剰摂取に繋がる場合があります。
【血糖が高いと言われている方】
特にスポーツドリンクは糖分が多く、多飲は高血糖の原因になります。
"飲み込みが難しい方には"
当社の給食室では、とろみ剤で水分にとろみをつけて摂取する方法と、
ゼリーで接種する方法を併用しています。
この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム
名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。
編集方針はこちら





