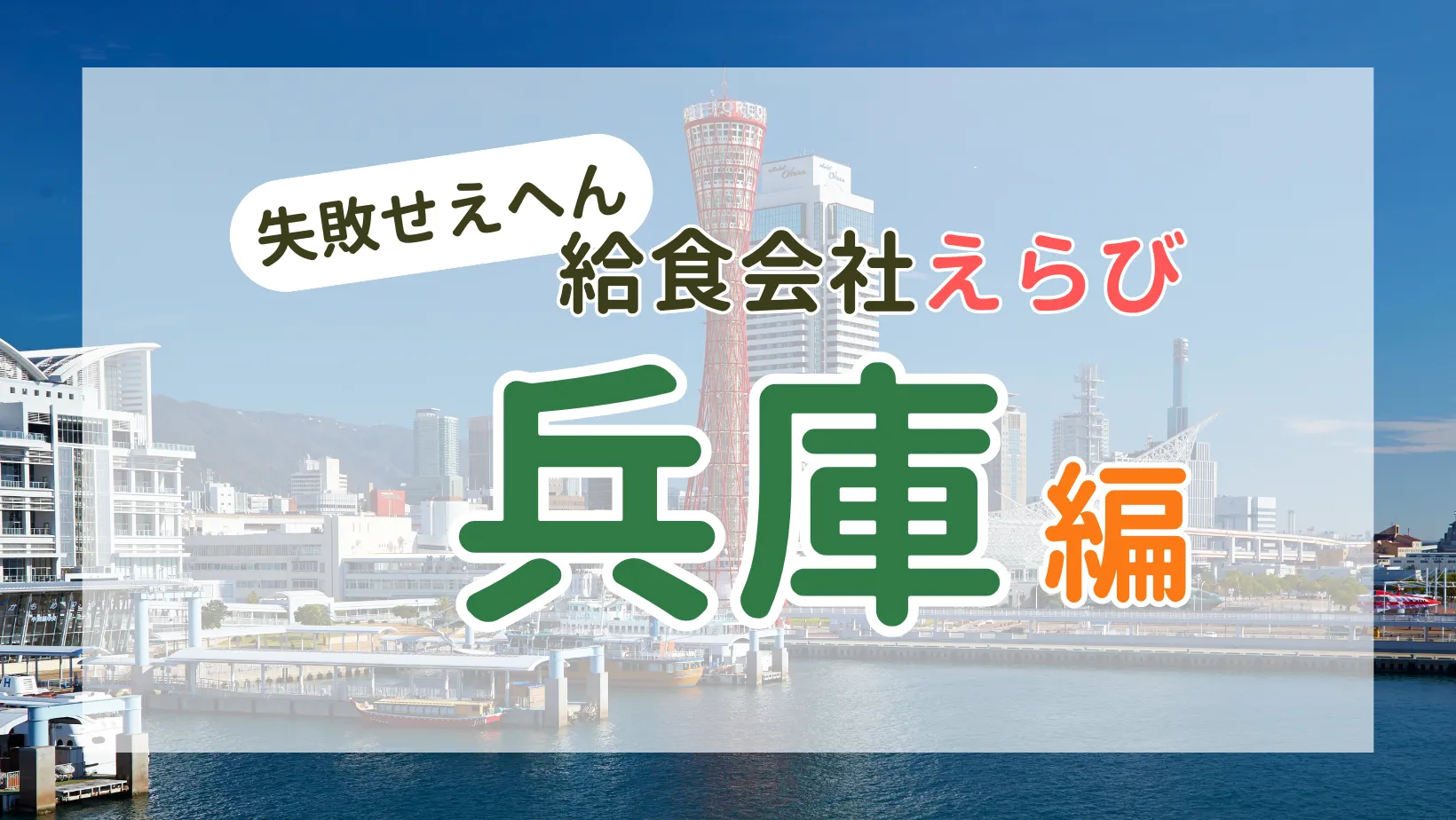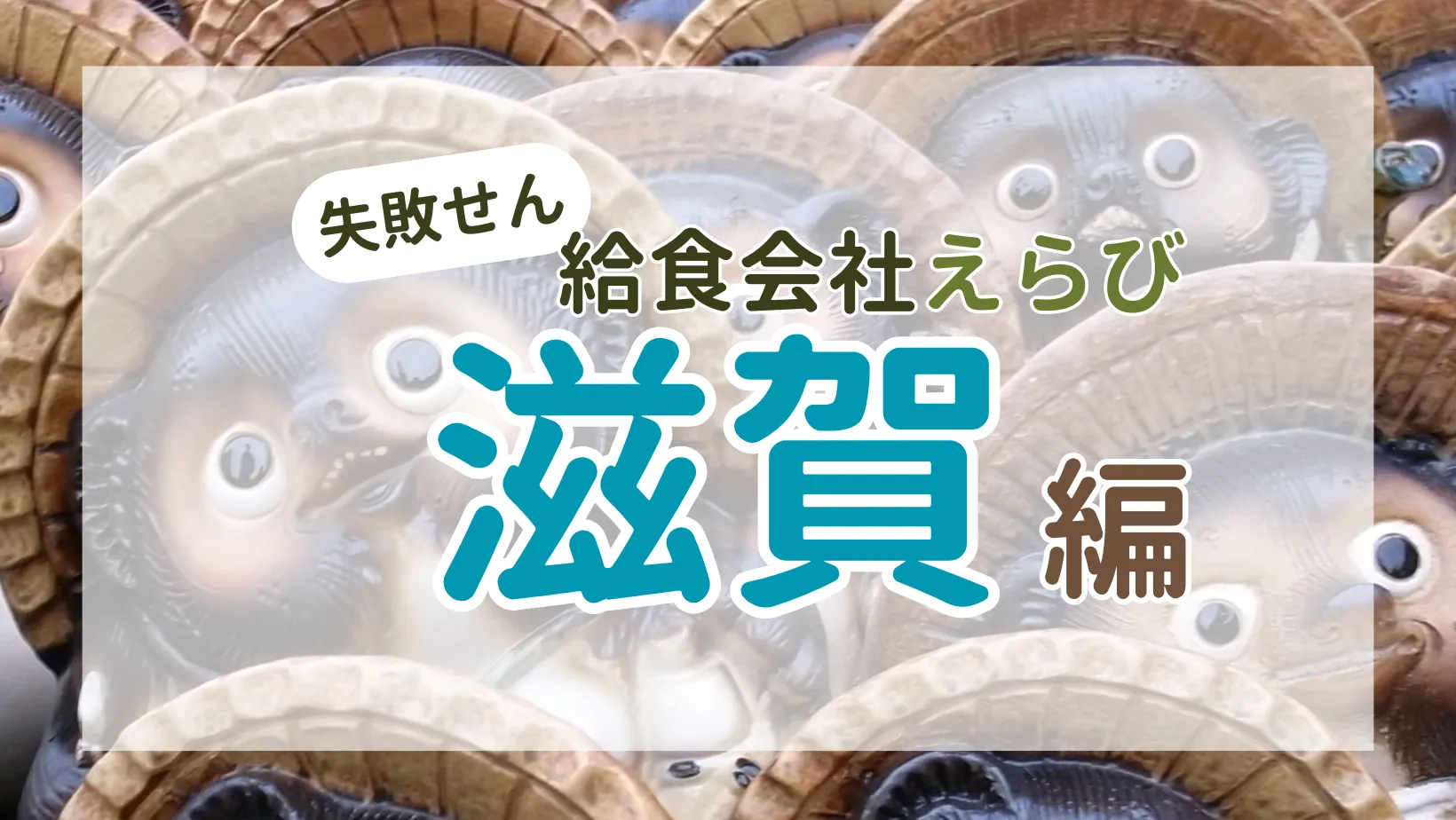カレーから異臭が・・・ウェルシュ菌に注意!

「カレーは2日目がおいしい」とよく言われますが、少し置いておいたカレーから、酸っぱいにおいや腐敗臭がすることはありませんか?実は、カレーは非常に腐りやすい食べ物でもあります。
今回は、カレーにおいの原因と、対策について解説します。
この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム
名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。
1.カレーのにおい・異臭の原因
カレーが異常なにおい(すっぱい匂い・納豆のようなにおい)を放つことがあります。これは、食中毒の原因にもなるウェルシュ菌が増殖している可能性があるため、十分な注意が必要です。特に長時間放置されたカレーには注意し、安全かどうか確かめることが大切です。
また、カレーに以下のような見た目・形状の変化がある場合にも十分に注意しましょう。
- 変色が見られる(表面が白っぽい)
- カビが生えている
- 糸を引いている
2.ウェルシュ菌とは?
カレーから不快な臭いがする場合、その原因の一つとしてウェルシュ菌の存在が考えられます。ウェルシュ菌は、微生物の一種で、特に土や水、動物の腸内に広く見られる普通の細菌なのですが、特別な条件下で体に害を及ぼすことがあります。
(1)特徴
ウェルシュ菌は、微生物の一種で、特に土や水、動物の腸内に広く見られる普通の細菌なのですが、次のような特徴があります。
- 食べ物とともに人の腸に達し、腸で毒素を作り、食中毒を引き起こす
- 酸素の少ない状態で増殖する
- 100℃、1~5時間の加熱でも耐える
ウェルシュ菌は、体内に入ると腸管内で増殖して芽胞をつくりますが、芽胞をつくるときにエンテロトキシンという毒素をつくります。その毒素によって、下痢や腹痛といった食中毒特有の症状があらわれます。下痢やおう吐もありますが、発熱はあまりありません。
ウェルシュ菌が増加しやすい環境は室温(43℃~47℃)・無酸素状態であるため、カレーなど、冷めにくく・中心部分の酸素が少ない食品を室温で長時間放置すると、ウェルシュ菌が増殖しやすい環境が整ってしまいます。
しかも恐ろしいことに、ウェルシュ菌がつくる芽胞(細菌の胞子のようなもの)は熱抵抗性が強く、100℃で再加熱しても生き残ってしまいます。
つまり、ウェルシュ菌が原因となる食中毒を防ぐには、いかにウェルシュ菌を増やさないかが非常に重要です。
(2)給食病ともいわれるウェルシュ菌食中毒
ウェルシュ菌は、一度に大量の食事を調理した給食施設などで発生することが多く「給食病」とも言われます。
カレーの他にも、シチュー、スープ、麺つゆからも確認されることが多く、原因としては厨房の人手不足から、食べる前日や2時間以上前にに大量に加熱調理し、大鍋のまま室温で長時間放冷されること、などがあります。
▶サイト内 施設向けサービス「ハイブリッド給食」ページを見に行く。
3.ご家庭で安全にカレーを食べるために
(1)常温のまま放置しない
カレーを含めた食品を安全に保存するためには、適切な温度管理が重要です。調理中の加熱は中心まで火がとおるように十分加熱し、調理完了から喫食まではできるだけ近付け、食べきるようにしましょう。
給食では、2時間以内喫食を基準としています。
(2)保存の際は、すばやく冷ます
加熱後、長時間保存する場合は、食品を小分けにして冷ますまでの時間を短縮しましょう。ウェルシュ菌が増殖しやすいのは50℃前後となるので、小分けにした方がすばやく温度を下げることができます。
密封して、冷水中で攪拌しても速やかに冷却することが可能です。
(3)再加熱の際は中心までしっかり加熱する
冷却した食品は喫食前に再加熱を十分に行いましょう。特に中心部に酸素が少ないカレーやシチューは混ぜ合わせて空気を触れさせながらあたためましょう。
4.まとめ
今後は、梅雨から本格的な夏となり、日本特有のジメジメした高湿度高温となります。キッチンや厨房内温度もそれ以上になると思われます。
安全安心な食事を楽しむためにも、調理前・調理中・調理後の温度管理に気をつけていきましょう。
無料資料ダウンロード
無料資料ダウンロード
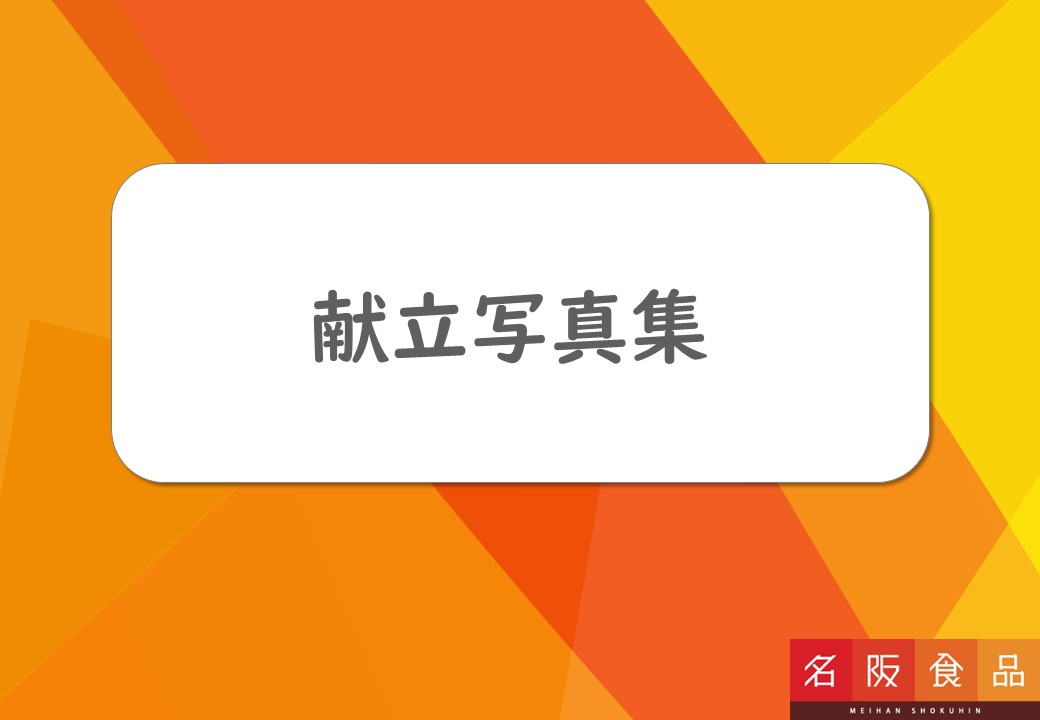
献立写真集の資料を
ダウンロードいただけます

キラッと光るレシピ集の資料を
ダウンロードいただけます