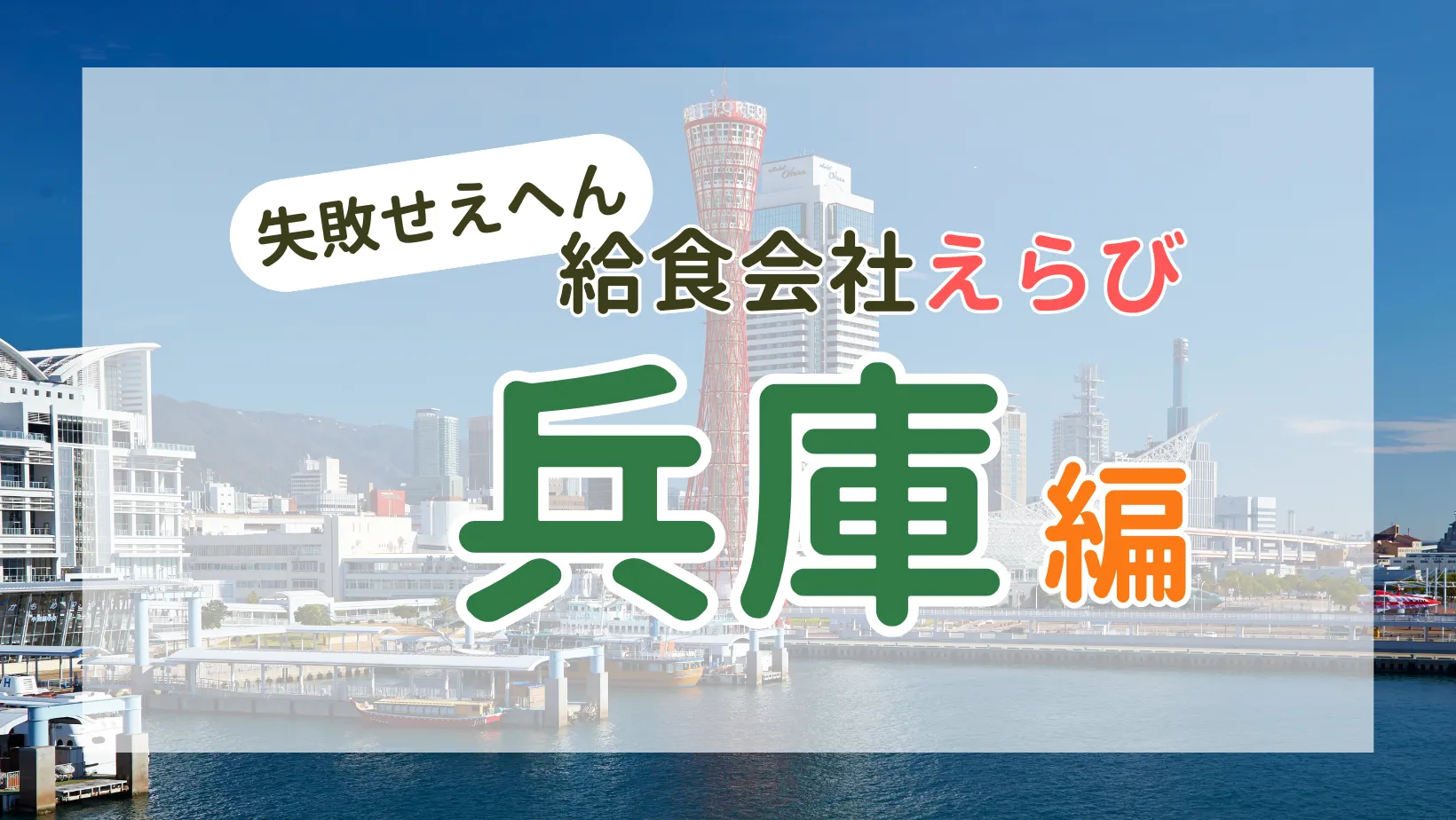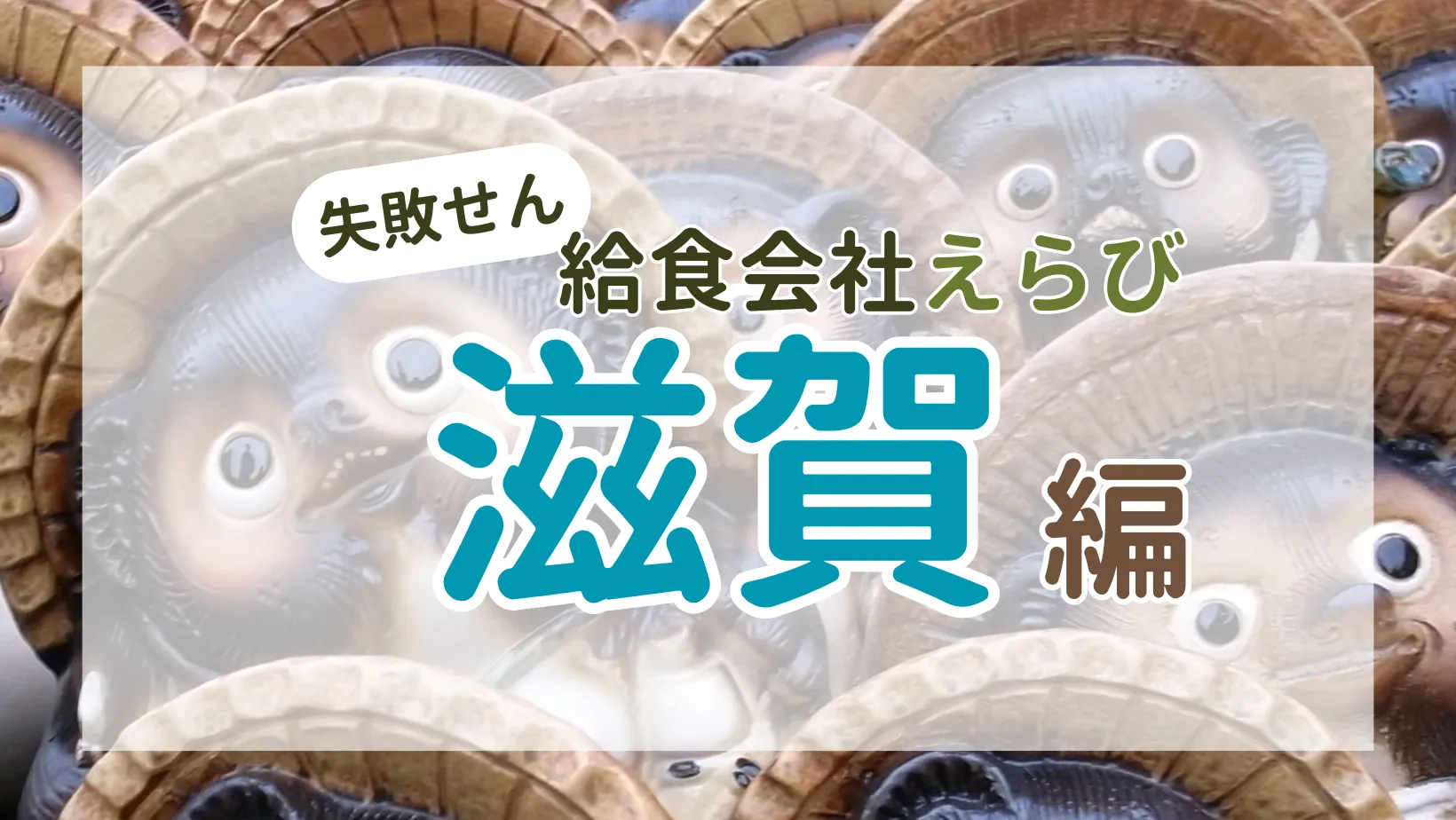給食におけるフードロス(食品ロス)問題……。給食委託会社ができることとは?

国内外問わず問題となっている「フードロス(食品ロス)」。
小売店や製造業、飲食店や家庭などあらゆる場所で発生している社会問題です。
もちろん給食も例外ではなく、フードロスを起こさないための対策が求められています。
この記事では、フードロスとはどのような問題であるかをはじめ、
その原因や給食におけるフードロスへの取り組みなどについて紹介していきます。
この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム
名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。
1.フードロスとは?
フードロス(食品ロス)とは、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品を指します。
近年メディアでもこの問題が取り上げられることが増えたため、
最近できた言葉と思う方もいるかもしれません。
しかし、約30年前からすでにフードロスに関する問題提起は行われており、
今もなお解消されていない課題なのです。
食品廃棄との違いは?
また、「食品ロス」と同じ意味でとらえられることも多い「食品廃棄」ですが、その定義は異なります。
「食品廃棄」は可食部だけでなく、果物の皮や種、肉や魚の骨など、
もともと食べられない部分を捨てる場合にも該当します。
2021年の食品ロス量
農林水産省が2021年11月に公表した「食品ロス量(令和元年度推計値)」によると、
年間の国内食品ロス量は約570万トンにもなります。
国民一人当たりがお茶碗約1杯分(約124グラム)の食べ物を毎日捨てている計算になり、
約570万トンの内およそ261万トンは家庭関係で発生しています。
また、農林水産省の「食品ロス量の推移(平成24~令和元年度)」を見ると、
約646万トンの食品ロス量だった平成27年度(2015年度)以降、その量は減少傾向に。
食品ロス削減に向けた取り組みがさらに活発化してきていることがうかがえます。
出典:農林水産省「日本の食品ロスの状況(令和元年度)」
出典:農林水産省「食品ロス量の推移(平成24~令和元年度)」
2.フードロス(食品ロス)の原因
ここでは、フードロス(食品ロス)が発生する主な原因を紹介していきます。
原因①:賞味期限・消費期限切れによる廃棄
フードロスの一因に挙げられることとして、保管していた食品が賞味期限・消費期限切れなどで、
手つかずのまま捨てられてしまうケースがあります。
また、売れ残りや返品などによっても食品ロスが発生しています。
買い過ぎや長持ちしない保存方法を改善することで、廃棄量を削減できるでしょう。
原因②:調理するときの過剰除去
過剰除去とは、調理工程で可食部分を廃棄することです。
野菜・果物の皮を厚く剥きすぎたり、お肉の脂身部分を捨てたりといった調理の仕方がこれに該当します。
なお、食べるのが困難な魚の骨、野菜や果物の皮の廃棄は過剰除去には該当しません。
過剰除去は、調理方法の見直しや工夫により低減できます。
原因③:食べ残し
「料理の作り過ぎ」「食べ物の好き嫌い」「冷蔵庫内の食材を放置して忘れる」などの
食べ残しもフードロスの原因の一つです。
食べ切れる量を調理したり、嫌いな食材でも食べられるよう調理や味付けを工夫したりすることで、
フードロス削減につなげられます。残さず食べる習慣を身につけていくことも重要です。
3.給食におけるフードロス(食品ロス)
給食の現場でも、フードロスが発生しています。
環境省の「学校給食から発生する食品ロス等の状況に関する調査結果について(お知らせ)」によると、
小学校・中学校における学校給食では、
食品廃棄物は児童および生徒一人あたり約17.2キログラム生じていることがわかりました。
給食のフードロスが発生している理由として、
食べ物の好き嫌いや多すぎる給食の量、給食を食べる時間の短さなどが挙げられます。
出典:環境省「学校給食から発生する食品ロス等の状況に関する調査結果について(お知らせ)」
給食でフードロスを削減するために
好き嫌いをせずに食べられることももちろん大切ですが、
子どもが苦手になりがちな野菜料理や魚料理を子ども向けメニューにしていくことも必要です。
また、たくさん食べる子どももいれば小食な子どももいます。
小食な子どもに対して普通の量を食べきるように無理強いすることは、
その子のストレスにもなりかねません。
全員に普通の量を固定して食べさせるのではなく、
個人の食べられる量に合わせて給食の量を調整すれば、食べ残しを減らせるでしょう。
4.給食委託会社の対策とこれから
フードロスは、2015年に国連によって採択が行われたSDGs(= 持続可能な開発目標)の
解決すべき課題の一つとされており、給食委託会社も取り組んでいくべき事項です。
すでに多くの給食委託会社がフードロス対策に乗り出しています。
調理時に発生するフードロス対策として、カット方法を変えたり、
野菜の皮まで調理したりとさまざまな工夫が実施されています。
ほかにも、地元の農業者が廃棄する予定の玉ねぎやにんじんを給食委託会社で買い取り、
給食の材料に取り入れるケースもあります。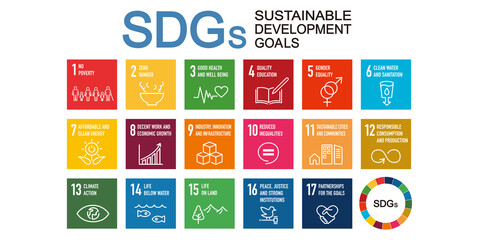
名阪食品の取り組み
名阪食品でも、食べ残しが出ないようメニューを作成したり、
調理方法を工夫したりするなど、フードロス削減に向けた取り組みを実施。
食材廃棄部分が発生しないよう、食材として美味しく食べられるような工夫もしています。
たとえば、出汁をとる際使用する昆布は廃棄されがちな食材ですが、
具材のひとつとして汁物で活用。
ほかにも大根葉を使用したり、野菜の皮を漬物にしたりと、
食材を大切に扱いながら利用者様に喜んでいただけるメニューの考案に取り組んでいます。
また、幼稚園・保育園での食育を通じて、園児様に「食」や「食材」の大切さへの理解を深めていただくなど、
多角的にフードロスという社会問題と向き合っています。
5.個人でも組織でも取り組むべき
フードロスの問題
フードロスはSDGsでも設定されている世界的な目標ですが、これらを解決するためには個人や組織が自分事として取り組む姿勢が大切です。
この記事を参考に、調理時の工夫や廃棄の仕方など、
まずは始められそうなことから挑戦していきましょう。
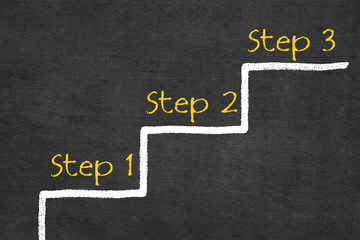
給食の外部委託を検討する際は、
給食委託会社がどのようなフードロス対策を行なっているのかにも着目してみてください。
名阪食品が行っているフードロス削減の取り組みについてご興味のある方は、
ぜひ下記よりお問合せください。
無料資料ダウンロード

サンプル献立を
ダウンロードいただけます

こちらの導入事例資料を
ダウンロードいただけます