介護施設の備蓄品と非常食に見直しを|予期せぬ災害に備えよう

2024年1月に発生した能登半島での地震に際し、心よりお見舞い申し上げます。当震災を受け、介護施設の備蓄品や非常食の備えができているか不安を感じた方もいるのではないでしょうか。急な災害に備えるための備蓄品や非常食は、使いやすいと思っていても実はあまり役立たなかったり、気が付いたら賞味期限が過ぎていたりするものもあります。本当に備えておくべきものは何なのか、量や保管場所などを改めてチェックしておきましょう。
※また合わせて、サイト内におきまして「幼保育園 お悩み解決」「特養・老健 お悩み解決」「社員食堂・寮 お悩み解決」に関する記載もご用意しております。是非ご参考になさって下さい。
▶サイト内 お悩み解決「こども園・保育園・幼稚園」ページを見に行く。
▶サイト内 お悩み解決「特養・老健」ページを見に行く。
▶サイト内 お悩み解決「社員食堂・寮」ページを見に行く。
この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム
名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。
編集方針はこちら
1.日本における災害の歴史
日本は、地形や地質、気象などの自然的条件により、台風や地震、津波などの自然災害が多い国です。これまでどのような災害が発生していたのか、2000年以降に発生した災害を振り返ってみましょう。
| 発生年月日 | 名称 | 被害状況 |
| 2000年9月 | 台風14、15、17号(愛知県など) | 死者10名、行方不明者2名 |
| 2004年8月 | 台風16号(香川県など) | 死者14名、行方不明者3名 |
| 2004年10月 | 新潟県中越地震(M6.8) | 死者68名 |
| 2005年12月~ 2006年1月 |
豪雪(新潟など) | 死者151名 |
| 2007年7月 | 新潟県中越沖地震(M6.8) | 死者15名 |
| 2008年6月 | 岩手・宮城内陸地震(M7.2) | 死者17名、行方不明者6名 |
| 発生年月日 | 名称 | 被害状況 |
| 2011年3月 | 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)(M9.0) | 死者1万5,000名以上、 行方不明者2,500名以上 |
| 2014年8月 | 豪雨(広島県など) | 死者77名 |
| 2014年9月 | 御嶽山噴火 | 死者58名、行方不明者5名 |
| 2018年7月 | 豪雨(広島県など) | 死者237名、行方不明者8名 |
| 2019年10月 | 台風19号(福島県など) | 死者104名、行方不明者3名 |
| 2020年7月 | 豪雨(熊本県など) | 死者84名、行方不明者2名 |
| 発生年月日 | 名称 | 被害状況 |
| 2021年2月 | 福島県沖地震 | 死者2名 |
| 2021年7月 | 熱海市伊豆山地区土砂災害 | 死者27名、行方不明者1名 |
| 2021年8月 | 大雨(長崎県など) | 死者13名 |
| 2022年3月 | 福島県沖地震 | 死者3名 |
| 2024年1月 | 能登半島地震 |
死者238名、安否不明19名 |
2.必要な備蓄品と非常食について
地震や台風などの災害時には、多くのライフラインが滞ってしまうため、備蓄品と非常食を準備しておく必要があります。万が一ライフラインがストップしてしまった際に、備蓄品や非常食が不充分だと、栄養不足から健康被害が生じる危険があります。また、施設内に食材があったとしてもガスや電気が使用できなければ調理できません。そのため、調理しなくても食べられるものを用意しておくことが大切です。
さらに介護施設では、準備しておくものの内容や量にも留意する必要があります。介護施設を利用している方のなかには、嚥下機能や咀嚼機能が低下していたり、一人で日常生活を送るのが困難だったりする利用者もいるためです。基本的な備蓄品や非常食以外にも用意するべきものがたくさんあるため、確認しておきましょう。
(1)必要な備蓄品・非常食の種類を知ろう
 毛布や懐中電灯、衛生用品などの基本的な備蓄品に加え、介護施設ではおんぶひもやマットレス、簡易ベッドなど避難する際に使うものを用意しておく必要があります。さらに総合栄養食品や経口補水液、とろみ調整用食品なども用意しておきましょう。非常食としては「水」「米」「フリーズドライ」「缶詰」の4つが基本です。
毛布や懐中電灯、衛生用品などの基本的な備蓄品に加え、介護施設ではおんぶひもやマットレス、簡易ベッドなど避難する際に使うものを用意しておく必要があります。さらに総合栄養食品や経口補水液、とろみ調整用食品なども用意しておきましょう。非常食としては「水」「米」「フリーズドライ」「缶詰」の4つが基本です。
水は飲むためだけでなく、うがいや手洗い、食べ物をやわらかくする、傷の洗浄などのためにも利用できます。米は炊飯器やガスが使用できないケースを想定し、そのまま食べられるパックご飯や水を注ぐだけで食べられるアルファ化米を用意しておくと良いでしょう。
フリーズドライ食品は、水さえあれば美味しく食べられます。味付け済みのものが多いので、栄養価や好みを考えながら、好きなものを揃えやすく便利です。密閉性が高く酸化しにくい缶詰も、スープや固形物などさまざまな食品があるため準備しておきましょう。
用意する際は、フリーズドライや缶詰のなかから、利用者の健康状態に対応したものを選んでバランス良く揃えておくことが大切です。また、停電や断水などにより、給湯器やガス機器が使えなくなるケースもあるため、食べ物は「水なしでも食べられるもの」と「水があれば食べられるもの」の2種類を用意しておきましょう。
(2)備蓄品・非常食の適切な量とは
 農林水産省によると、備蓄品や非常食の備蓄量の目安は3日分とされています(※1)。可能あればそれ以上の備蓄を検討しましょう。大規模災害が発生した場合、介護施設では利用者や従業員のほか、災害発生時に来所していた見舞客やボランティアにも対応する必要があります。曜日や時間帯により異なりますが、これまでどの程度の方が訪問しているのか考慮して、最大人数分を準備しましょう。
農林水産省によると、備蓄品や非常食の備蓄量の目安は3日分とされています(※1)。可能あればそれ以上の備蓄を検討しましょう。大規模災害が発生した場合、介護施設では利用者や従業員のほか、災害発生時に来所していた見舞客やボランティアにも対応する必要があります。曜日や時間帯により異なりますが、これまでどの程度の方が訪問しているのか考慮して、最大人数分を準備しましょう。
| 備蓄量の目安 | |
| 水 | 1人あたり1日3L(※1) × 3日分 計9L |
| 保存食 | 1人あたり1日3食 × 3日分 計9食 |
| 毛布 | 1人1枚 |
| その他 | 物資ごとに必要量を算定 |
外部の帰宅困難者が来所すると仮定して、余裕を持って備蓄しておくとさらに安心です。
(3)行備蓄品・非常食の保管場所を決めよう
災害時に使う食品や飲料は、必要なときにサッと取り出せるよう、「施設内の低い場所」に分散させて保管することが重要となります。保管する際は、以下の条件を満たせる場所がおすすめです。
| ・倒壊や浸水などの被害を受けにくい場所 |
|
・調理スペースが大きな被害を受けそうな場合 |
|
・屋外の倉庫に凍結リスクがあったり、高温多湿であったりと、 |
どの場所が最善かは、食器や調理に必要な水なども併せて保管することを考慮して検討しましょう。なお、「保管場所からどのように持ち出すか」「どこから保管場所へアクセスするか」を職員全員が把握していることも大切です。
(4)賞味期限が迫った非常食の活用について
備蓄品や非常食は、長期保存できるように作られていますが、食糧により賞味期限が異なります。そのため、適宜見直さないと「気が付いたら賞味期限が過ぎていた」ということにもなりかねません。 実は、食品の賞味期限は実際よりも2割以上短く設定(※2)されていることがほとんどです。適正な状態で保存された備蓄食料であれば、賞味期限が少し過ぎていても食べられると留意し、食品ロスを防ぎましょう。賞味期限切れを防ぐには、非常食を普段の食事のなかで定期的に使用し、使ったものを補填する「ローリングストック法」を取り入れることがおすすめです。
実は、食品の賞味期限は実際よりも2割以上短く設定(※2)されていることがほとんどです。適正な状態で保存された備蓄食料であれば、賞味期限が少し過ぎていても食べられると留意し、食品ロスを防ぎましょう。賞味期限切れを防ぐには、非常食を普段の食事のなかで定期的に使用し、使ったものを補填する「ローリングストック法」を取り入れることがおすすめです。なお、非常食の活用レシピには以下のようなものがあります。
●乾パンや保存用ビスケットをリゾットやデザートに
そのままでは硬い乾パンも、牛乳に浸して電子レンジで加熱し、コンソメをかけたりチーズを乗せたりすればリゾットになります。
また、保存ビスケットは袋に入れて割り、ナッツやドライフルーツ、弱火で溶かしたバター、牛乳、ココアパウダー、砂糖と混ぜ、成形後2時間ほど冷凍庫で休ませるとチョコサラミに。薄くスライスしていただきましょう。
●アルファ化米をパエリア風にアレンジ
 味が染み込みやすいアルファ化米は、ミートソース缶やあさり(水煮缶)と炒めてパエリア風にするのも良いでしょう。ミートソース缶には玉ねぎやにんじん、トマトといった野菜のほか、たんぱく質源である肉が含まれているので、栄養面でもおすすめです。
味が染み込みやすいアルファ化米は、ミートソース缶やあさり(水煮缶)と炒めてパエリア風にするのも良いでしょう。ミートソース缶には玉ねぎやにんじん、トマトといった野菜のほか、たんぱく質源である肉が含まれているので、栄養面でもおすすめです。
非常食もアレンジすれば普段の食事として美味しく食べられるので、「備蓄食料の賞味期限を確認する日」を設け、賞味期限が短いものから消費していきましょう。
3.災害に備えて備蓄品や非常食を見直そう!
災害は、いつ起こるかわからず、いつか備えようと思っているうちに災害が発生することも考えられます。介護施設において、災害の際にも充分なケアを継続するためには、非常食や備蓄品などをしっかり備えておくことが大切です。利用者の体調や健康状態に合わせたものを揃えるのは大変かもしれませんが、施設で必要な備蓄品の内容や量を見直してみてはいかがでしょうか。

無料資料ダウンロード

献立写真集の資料を
ダウンロードいただけます
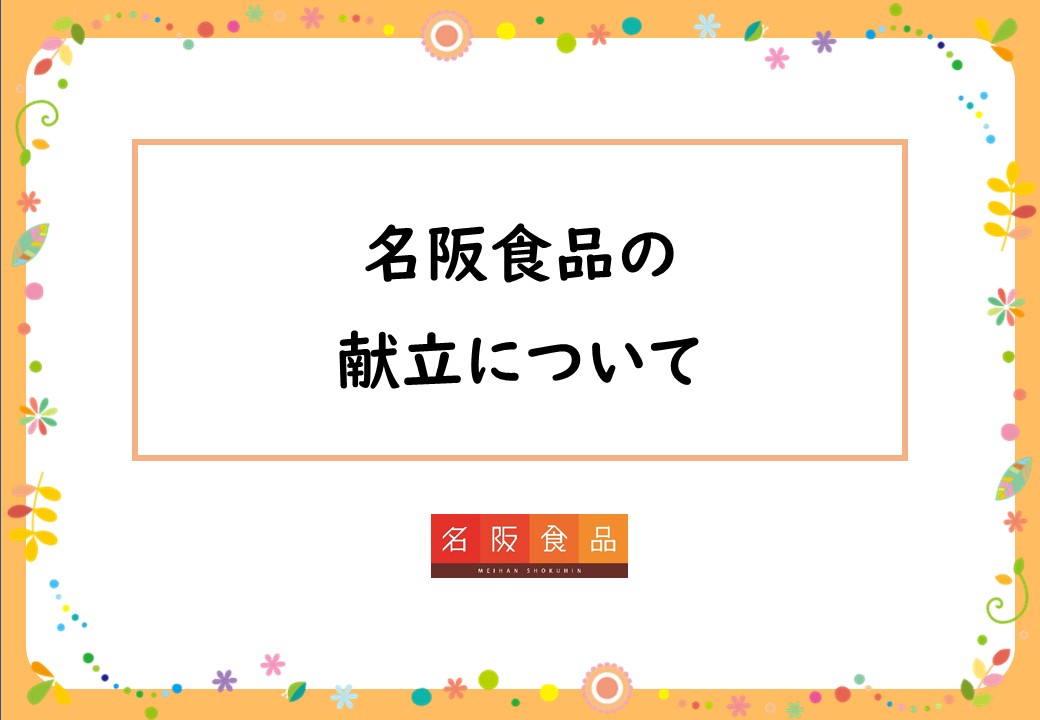
名阪食品の献立についての資料を
ダウンロードいただけます
無料資料ダウンロード
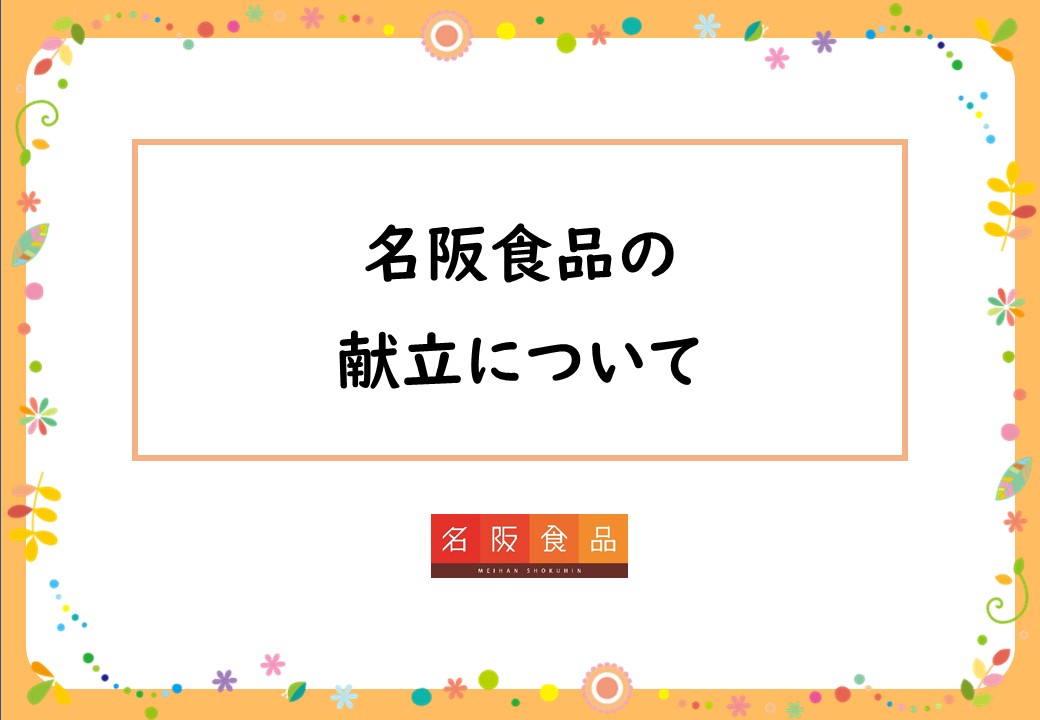
名阪食品の献立についての資料を
ダウンロードいただけます

食育実施例集の資料を
ダウンロードいただけます





