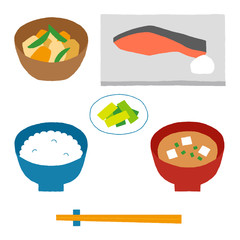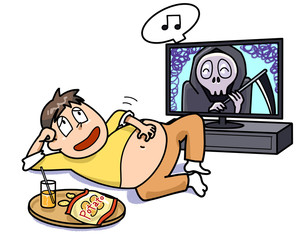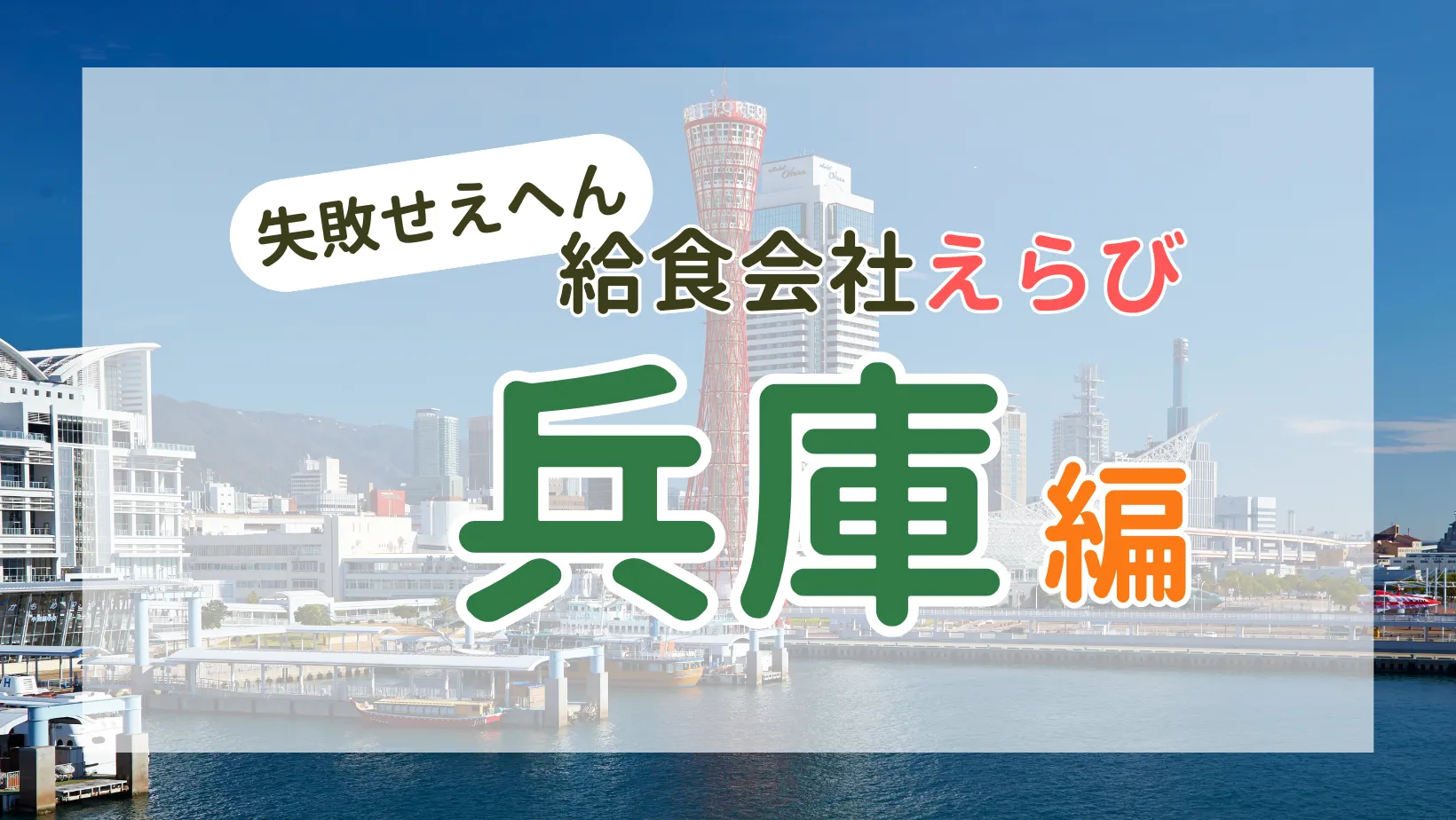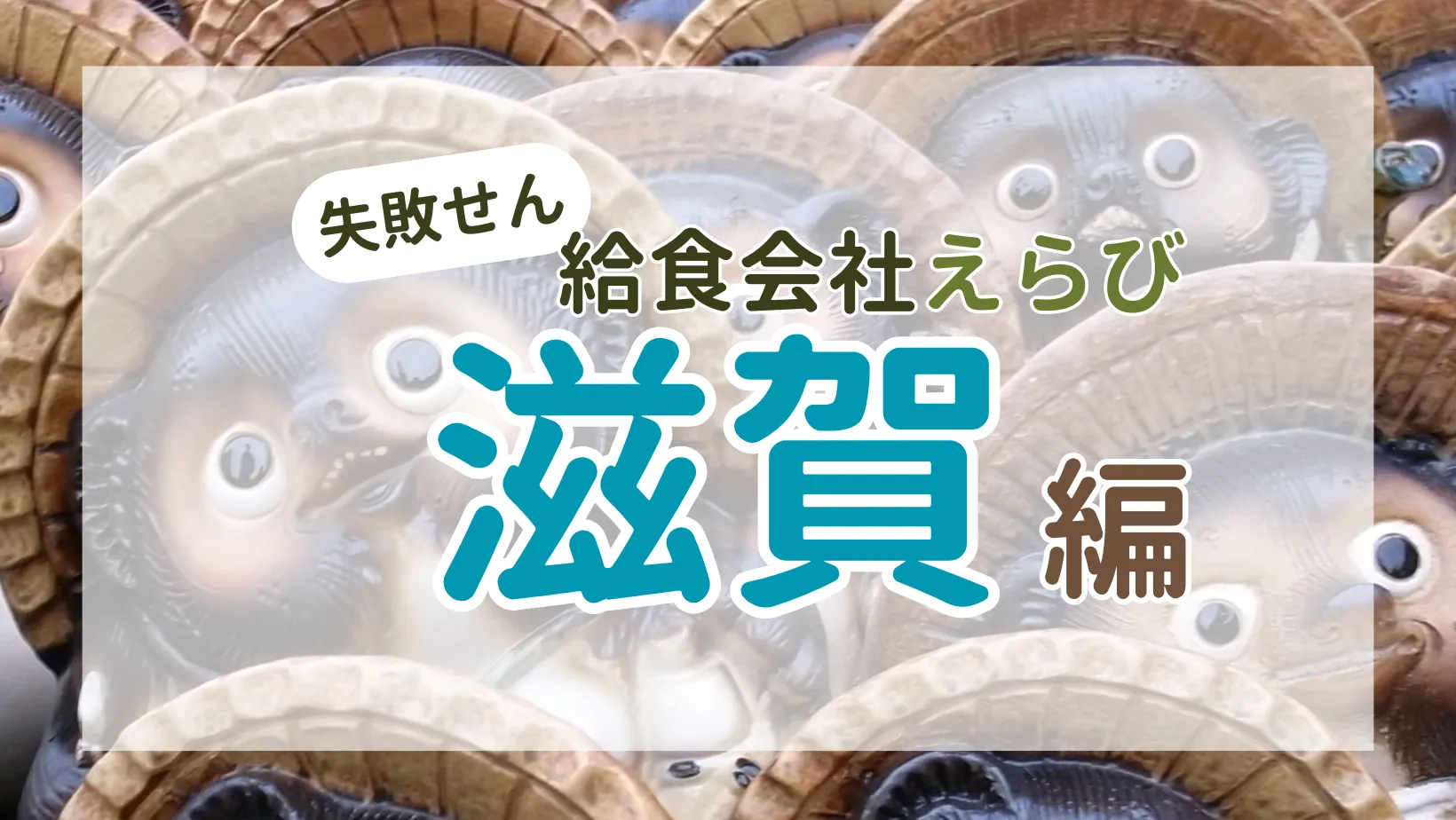食育ピクトグラム「テーマ3 バランスよく食べよう」を詳しく知ろう!

農林水産省が推進している食育ピクトグラムのテーマ3にもあるように、近年では「バランスの良い食事の摂り方」が重要視されています。しかし、毎食バランスの良い食事を摂ることは、実際にはなかなか難しいものです。そもそも、それがどういった内容の食事なのか把握できていない方もいるでしょう。そこで今回は、バランスの良い食事がどのような内容なのか、また、どうすれば簡単にバランスの良い食事が摂れるのかについて紹介します。
この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム
名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。
1.バランスの良い食事とは
バランスの良い食事というと、多くの野菜や食材を使用したメニューを思い浮かべる方もいるでしょう。しかし、実際にはそうではありません。ここでは、バランスの良い食事とはどういうものなのか、おすすめの食事の摂り方などを見ていきましょう。
(1)主食・主菜・副菜を毎食そろえよう
バランスの良い食事とは、主食・主菜・副菜をそろえた食事のことをいいます。主食とは、炭水化物であるごはんやパンなどを。主菜は、たんぱく質をメインにした肉や魚などを主材料にした料理を。副菜は、ビタミンやミネラル、食物繊維などを摂取するための料理を指します。この3つを意識することで、自然と栄養バランスがとれた食事になるでしょう。また、栄養面だけでなく彩りが良くなるため、食欲が増す効果も期待できます。
一日に必要な栄養素を摂るためには、前述したようなバランスの良い食事を一日3食、規則正しく食べることが重要です。農林水産省が発表した資料「『食育』ってどんないいことがあるの?~エビデンス(根拠)に基づいて分かったこと~」によると、一日にバランスの良い食事の回数が少ない人ほど栄養素不足であることがわかっています(※1)。
また、同資料内で病気と食事の関係を調査したものを参考にすると、肉類や加工肉、アルコール飲料、高塩分食品、油を多く使った料理を摂る人は、がんや循環器疾患のリスクが高まることがわかりました(※1)。病気のリスクを低くするためには、薄味を意識した減塩食にしたり、油を控えたりすると良いでしょう。また、夕食は控えめにし、その代わりに朝食はしっかり食べるという方法もおすすめです。
(2)「五大栄養素」を偏りなく食べよう
先ほどはバランスの良い食事に注目しましたが、ここでは、食事で摂取すべき栄養素について詳しく見ていきましょう。というのも、バランスの良い食事を実現するためには、五大栄養素を自分の身体に必要な分だけ摂取する必要があるからです。
五大栄養素とは、「糖質」「脂質」「たんぱく質」「ミネラル」「ビタミン」のことで、それぞれに役割があります。
表でわかる通り、五大栄養素にはさまざまな役割があり、人間が生きていくうえでどれも欠かせません。
(3)料理を乗せる皿の数をそろえよう
バランスの良い食事を実現するためには、「主食・主菜・副菜をそろえること」「一日3回の規則正しい食事を心がけること」のほかに、先に紹介した五大栄養素を偏りなく食べることも重要になります。五大栄養をカバーするためには、何をどれだけ食べるのかを考えていかなければなりません。ただし、人によって一日に必要な栄養素の量は異なるので、自分に必要な栄養素の量を把握する必要があると言えるでしょう。
そこで参考にしたいのが、農林水産省が発表している「食事バランスガイド」です(※2)。ここでは、一日に何をどれだけ食べるべきかを、主食・主菜・副菜のほかに果物、乳製品についてもそれぞれわかりやすく紹介しています。自分にとって一日に必要な量を把握して、料理を乗せる皿の数を把握すれば、簡単に一日に必要な量がわかるでしょう。
たとえば、一日に2,200キロカロリーほどのエネルギーを必要とした場合の組み合わせ例は以下の通りです。
| 主食 | 毎食しっかり食べる。太り気味の方、活動量が低かった日にはご飯の杜方を控えめに。 |
| 主菜 | 毎食たんぱく源は一皿食べることが望ましい。「肉料理」に偏らず「魚料理」も交互に食べること。「大豆製品」や「卵料理」も「主菜」としてカウントする |
| 副菜 | 野菜料理は1日5~6皿 |
| 果物 | 1日1皿 |
| 乳製品 | 1日1回 |
2.簡単にバランスの良い食事を摂る方法
バランスの良い食事が健康のために必要だということがわかっていても、日々の生活が忙しく、なかなか料理まで手が回らないこともあるでしょう。ここからは、簡単にバランスの良い食事を摂るための方法について紹介します。
(1)食べ方のクセを知ろう
まずは現状把握のために、普段の食生活を振り返ってみましょう。食べ物のクセを見つけることで、現状の栄養素の偏りや食事量を知ることができます。以下のようなクセがないかチェックしてみてください。
| 1.炭水化物(ご飯・パン・麺など)を好んで食べる。 2.間食が習慣化している。 3.たくさんの量を一度に食べられない。 4.主菜は満腹になるまで食べる。 5.好き嫌いは多い方だ。 6.食べるメニューが固定化している。 7.購入する食材やお惣菜は毎回ほぼ決まっている。 |
こういったクセがあると、食べるメニューが固定化していつも同じような食材を摂っている可能性があります。またビタミンやミネラルが不足しやすいでしょう。間食をやめられない人や炭水化物が好きという人は、太りやすくなっているかもしれません。クセを直して必要な栄養素を意識的に選択していき、食生活の改善を目指しましょう。
(2)たんぱく源をさまざまな食材から取り入れよう
もう一つは、たんぱく源がメインとなるよう、主菜の取り入れ方を工夫する方法です。たんぱく質は、筋肉や内臓をつくり、身体を動かす原動力になります。そのほかにも、体内に栄養や酸素を運んだり免疫機能を維持したりする働きもあることから、身体に必要不可欠な栄養素です。
また、タンパク源にはさまざまな栄養が豊富に含まれているという特徴があります。たとえば牛もも肉の場合、たんぱく質以外にビタミンB2・ビタミンB6・鉄・亜鉛などが、卵にはビタミンA・カルシウム・鉄が含まれています。
このことから、朝食・昼食・夕食で異なる主菜を摂取すれば、種類の違うビタミンやミネラルを効率的に摂取でき、簡単に栄養バランスを改善できることがわかるでしょう。ただし、料理に慣れた方でない限り毎食違う主菜を食事のたびに考えるのは難しいため、事前に一週間分の主菜を決めておくと買い物も料理も楽です。
ほかに、一食のなかに複数のたんぱく源を含めるという方法も良いでしょう。たとえば、焼き魚と卵焼き、豚の生姜焼きと冷奴などが挙げられます。しかしこの場合、たんぱく質の摂取量が増えやすいという傾向があり注意が必要です。自分に合った一日のたんぱく質量を、改めてチェックしておきましょう。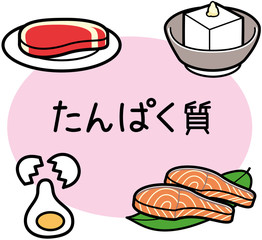
3.バランスの良い食事が健康な身体をつくる
バランスの良い食事を実践するためには、五大栄養素を意識した「主食」「主菜」「副菜」を摂取する必要があります。しかし、頭ではわかっていてもいざ実行に移すとなると難しいこともあるでしょう。
そこで「給食」を活用すれば、バランスの良い食事を確保できます。給食の献立を参考にすることで、どの栄養素がどれだけ必要なのかの指標にもなるはずです。バランスの良い食事を摂るために、給食を活用してまずは一歩踏み出してみましょう。
無料資料ダウンロード

献立写真集の資料を
ダウンロードいただけます
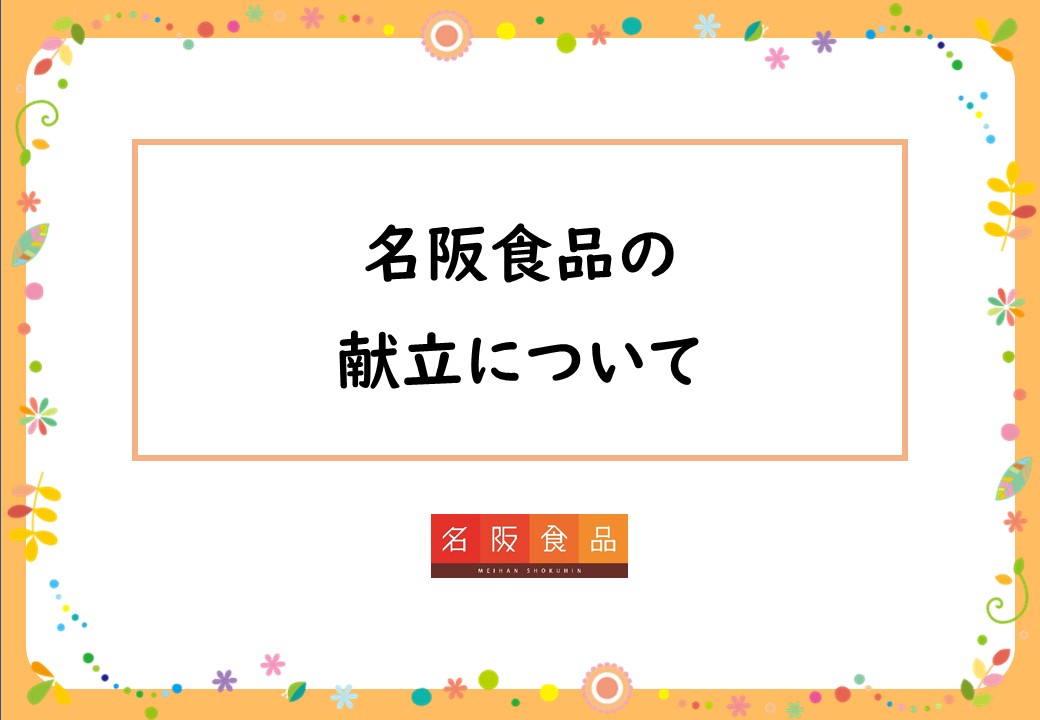
名阪食品の献立についての資料を
ダウンロードいただけます
無料資料ダウンロード
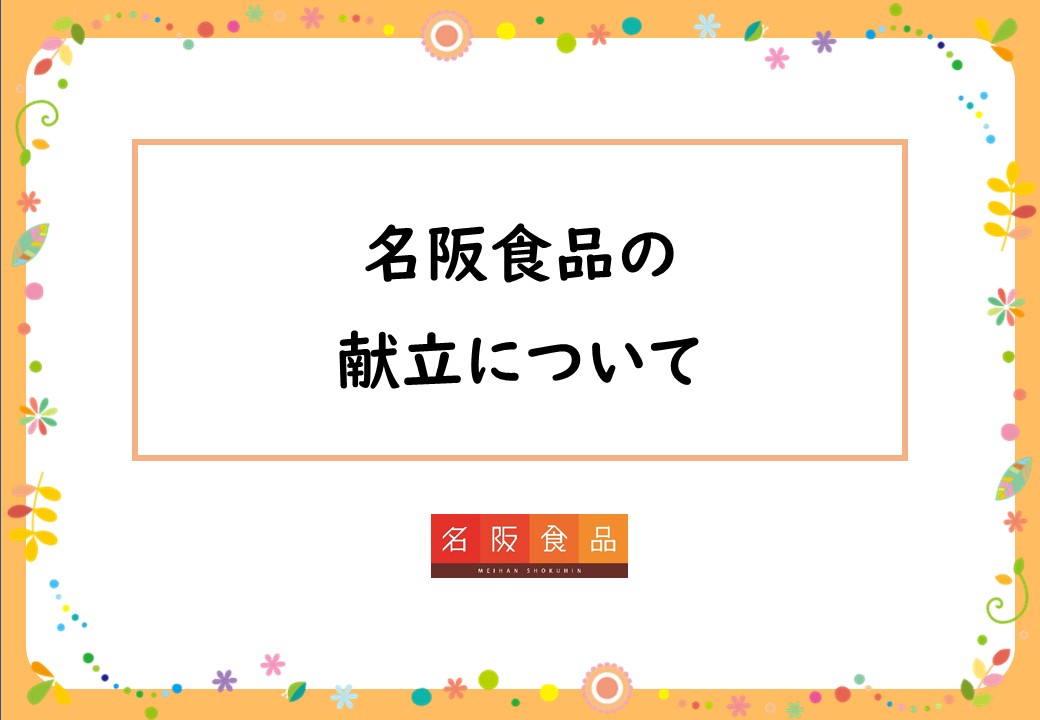
名阪食品の献立についての資料を
ダウンロードいただけます

食育実施例集の資料を
ダウンロードいただけます
【出典】
※1農林水産省「『食育』ってどんないいことがあるの?~エビデンス(根拠)に基づいて分かったこと~統合版 (令和元年10月) 」
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/evidence/attach/pdf/index-30.pdf
※2農林水産省「『食事バランスガイド』について」
https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/