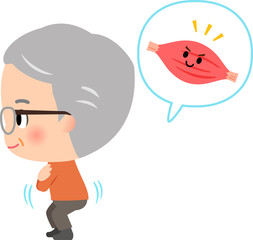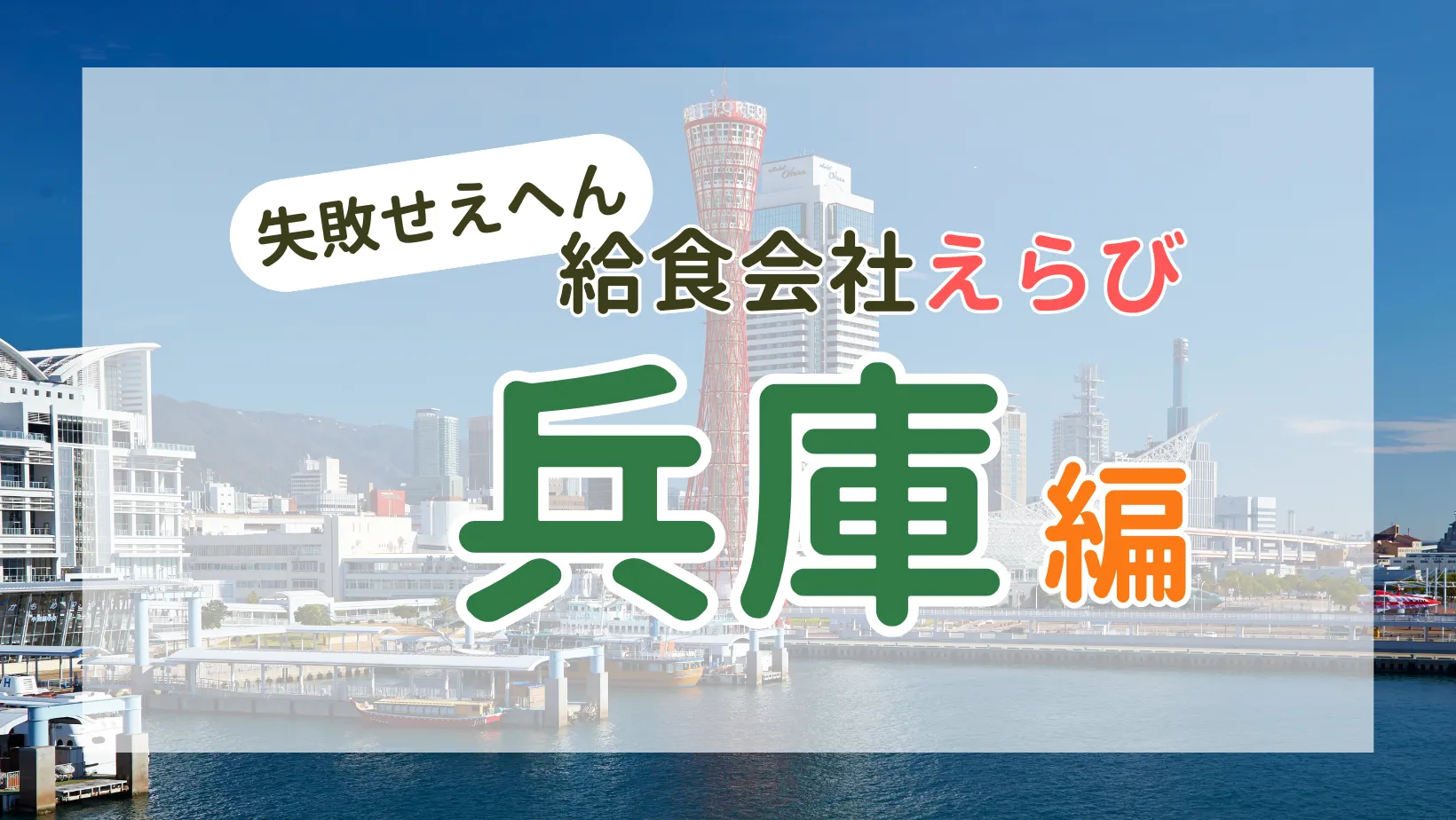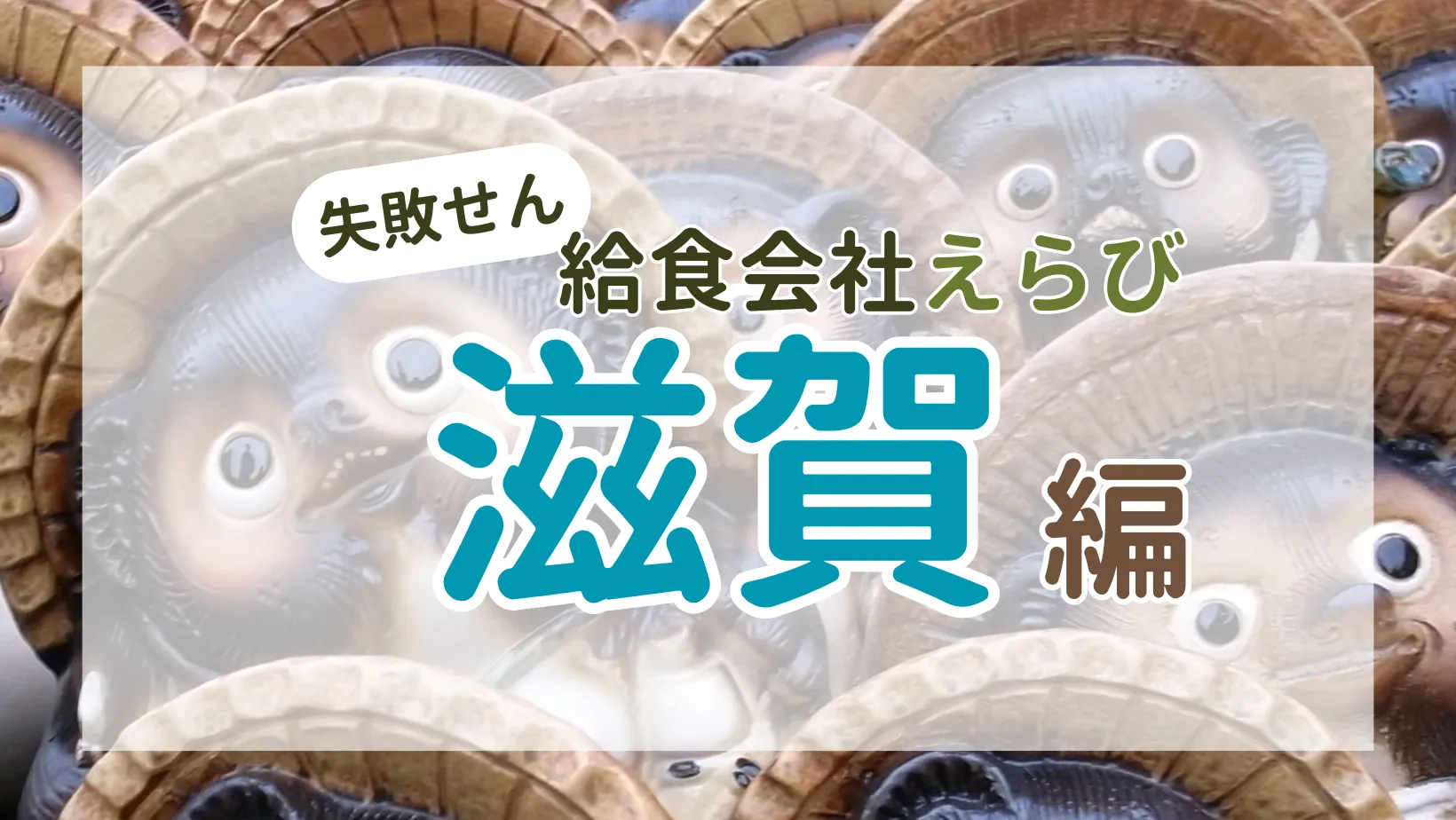食育ピクトグラム「テーマ2 朝ごはんを食べよう」を詳しく知ろう!

農林水産省では、誰にでもわかりやすく食育を発信するため、「食育ピクトグラム(絵文字)」を導入しています。今回はそのなかから「朝ごはんを食べよう」に注目しました。
最近、「朝ごはんが大切」という言葉を耳にする機会もあるでしょう。しかし、具体的にどのようなメリットがあるかご存じですか? ここでは、世間の朝食の摂取状況や世代別に見る朝ごはんのメリットを紹介していきます。忙しい、食欲がないなどの理由から、つい朝食を疎かにしてしまう方や、朝ごはんの重要性が気になる方は、ぜひチェックしてください。

この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム
名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。
1.朝ごはんの摂取状況
2016年に実施された農林水産省の調査によると、「朝ごはんをほぼ毎日食べる」と回答した成人は83.7%、中学3年生は83.3%、小学6年生が87.3%という結果が報告されています。
一方、朝食の欠食状況に関しては、成人は2009年では10.8%、2016年では11.4%が朝食をとっていませんでした。成人と比較すると少ないものの、中学3年生と小学6年生の朝食をとらない層も2016年ではそれぞれ6.6%、4.5%存在することがわかっています(※1)。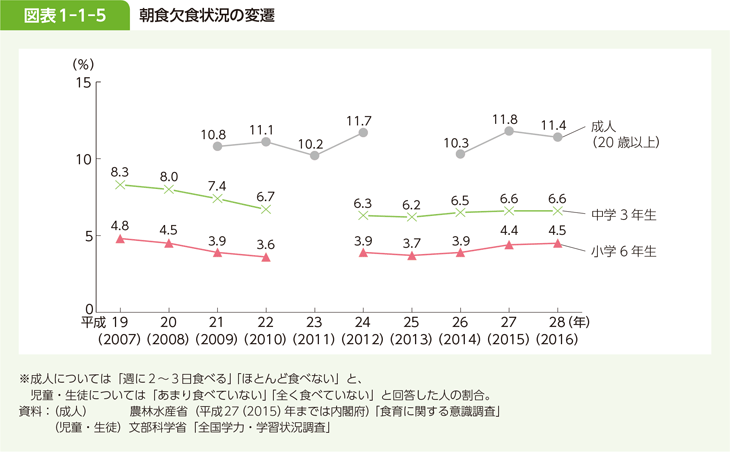
また、成人に対し朝食欠食が始まった時期を質問すると、「中学生や高校生の頃」と回答する人が2割程度いました。このことから、学生時代の朝ごはんの習慣が、成人になってもそのまま引き継がれる可能性がある、と言えるでしょう。また、調査年によって数値は異なるものの、朝食をとらない層は一定数いることもわかります。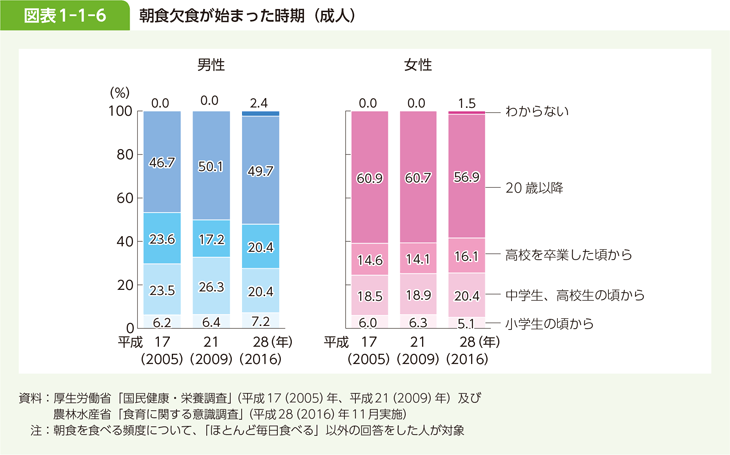
2.世代別、朝ごはんのメリット
ここでは、朝ごはんのメリットを世代別に紹介していきます。(1)幼少期

幼児期の朝ごはんは、生活リズムの定着に役立ちます。毎朝決まった時間に起き、朝ごはんをとることで、その後の一日のリズムも整っていくでしょう。また朝ごはんは、寝ている間に低下した体温や血糖値を上昇させる役割もあります。これにより、体内の動きと脳の働きを活性化させられるのです。加えて胃腸の動きも促されるので、便秘の予防・解消にも役立つでしょう。
さらに、朝ごはんを食べるか食べないかによって、自律神経の働きが変わってくる点も注目すべきポイントです。自律神経は、体を活動的にする神経とリラックスさせる神経をあわせ持ち、免疫力にも大きく関係してきます。朝ごはんをとって自律神経が整えば、心と身体が安定し、免疫力向上にもつながるとも考えられるのです。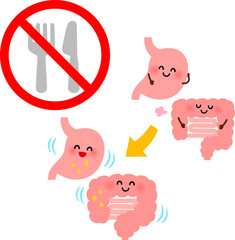
(2)小中高生

人間は、眠っている間にも脳のエネルギーを消費しています。そのため、朝ごはんを食べなければ、脳のエネルギー不足を引き起こしてしまうのです。一方、朝ごはんをとればブドウ糖を摂取でき、脳の働きを活発化させて記憶力・集中力を高められます。それにともない学力も向上していくでしょう。
また、睡眠の質が高まるのも朝ごはんを食べるメリットです。よく噛んで食べると、セロトニンが分泌され、それを材料に睡眠ホルモンであるメラトニンが作られます。ぐっすりと眠れて、翌朝もスッキリと目覚められるので、学校の遅刻も防げるようになるでしょう。
(3)大学生

実家を離れて一人暮らしをする人もいる大学生は、「自分で朝ごはんを用意するのが面倒くさい」「ぎりぎりまで寝ていたい」などの理由で朝食を抜いてしまうケースが見られます。しかし、朝ごはんの習慣には、体内時計を正常に整え、生活習慣病を予防するといったメリットがあるのです。
また、朝ごはんは腹もちが良いため、間食を減らせます。さらに脂肪を溜め込む働きのあるホルモンの分泌が緩やかになり、肥満予防にもつながるでしょう。脳のエネルギー源となるブドウ糖が摂取できることから、朝からやる気が高められ学力アップにも有効です。
(4)社会人

社会人にとっても、朝ごはんは重要な役割を担っています。朝ごはんを食べないでいると、空腹感が強まり、昼ごはんを食べ過ぎてしまう恐れもあるのです。昼ごはんでまとめて食べるよりも、食事回数を朝・昼・夜と分けることで1食分の食事量が抑えられ、肥満や生活習慣病の予防にもつながっていきます。
加えて、脳のエネルギー源となるブドウ糖を含む白米やパンなどの主食を朝ごはん時に摂取すれば、仕事の効率アップも図れるでしょう。社会人男女1000人を対象に東北大学が行った調査では、栄養バランスがとれた朝ごはんの習慣がある人は、生活の充実度が高い傾向にあることがわかっています(※2)。朝ごはんを摂取することで心身が安定するため、パフォーマンスを発揮しやすい状態が続き、結果的に生活の充実度が向上すると考えられます。
(5)高齢者

高齢者は、朝ごはんを食べることで生活リズムを構築しやすくなります。それにともない、体内のホルモンや消化酵素の分泌・神経調整・臓器組織の活性などのバランスを維持できるのです。また、日常の食欲と便通の安定にも期待できます。
また、高齢者は摂食・嚥下や口腔に関する問題、病気などによる食欲が低下するケースが多いとされています。さらに、身体機能の低下などにより買い物や調理が困難となり、習慣的な食事量が低下することもあります。こうした状態は、高齢者の低栄養状態を招く大きな要因となる恐れがあります。きちんと朝ごはんを食べるように習慣づけることで低栄養状態の回避も期待できるでしょう。また、タンパク質の摂取によって、低下しやすい筋肉量の向上も図れるはずです。
3.朝ごはんでどの世代も健康な生活を
忙しい毎日のなかで、朝ごはんを食べる習慣がないという人も少なくないはずです。しかし、朝ごはんを食べることで生活リズムの構築や健康維持、生活の充実度の向上など多くのメリットが得られます。どの世代においても、心身ともに健康的な生活を送るためには朝ごはんが不可欠と言えるでしょう。この記事を参考に、自身の朝ごはんの習慣を振り返り、さらに施設利用者様にも朝ごはんの大切さを呼びかける機会となれば幸いです。

無料資料ダウンロード

献立写真集の資料を
ダウンロードいただけます
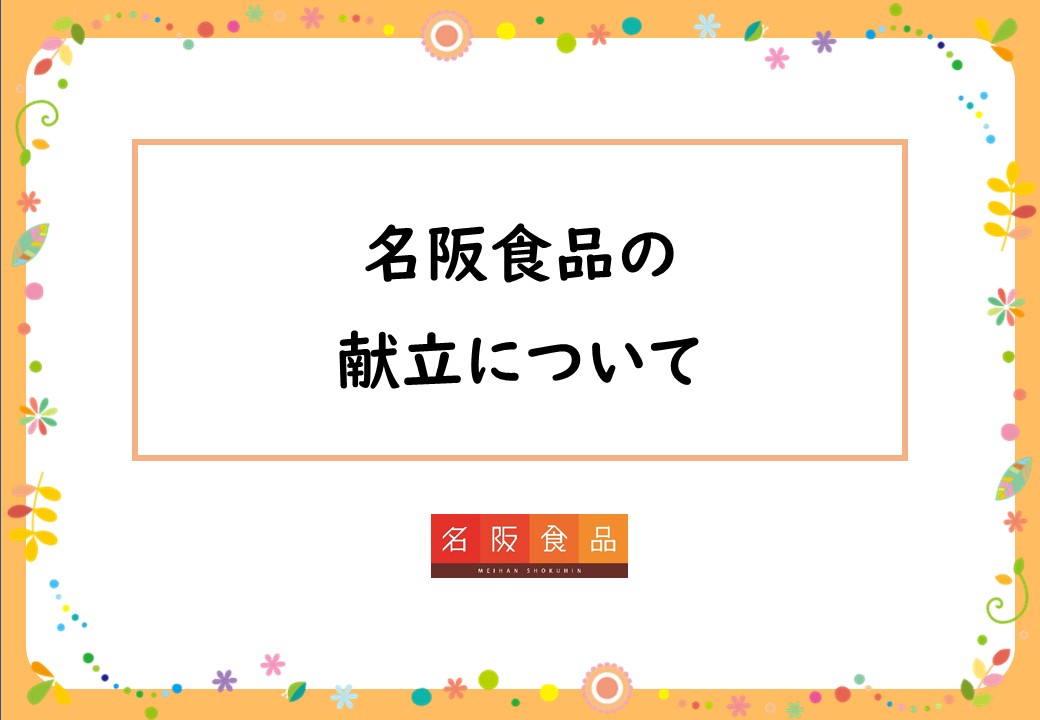
名阪食品の献立についての資料を
ダウンロードいただけます
無料資料ダウンロード
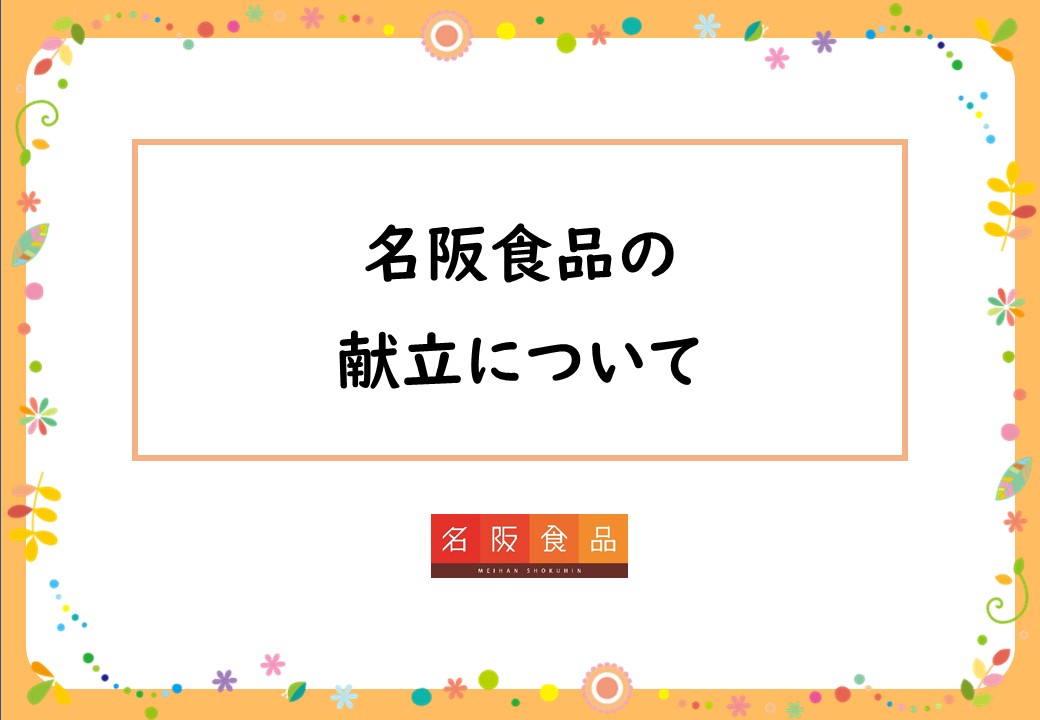
名阪食品の献立についての資料を
ダウンロードいただけます

食育実施例集の資料を
ダウンロードいただけます
【出典】
※1農林水産省「平成28年度食育白書(平成29年5月30日発表) 2朝食摂取状況」
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wpaper/h28/h28_h/book/part1/chap1/b1_c1_1_02.html
※2東北大学 加齢医学研究所 スマート・エイジング国際共同研究センター「幸せ度とライフスタイルに関する調査」
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohoku_univ_press2010091601.pdf