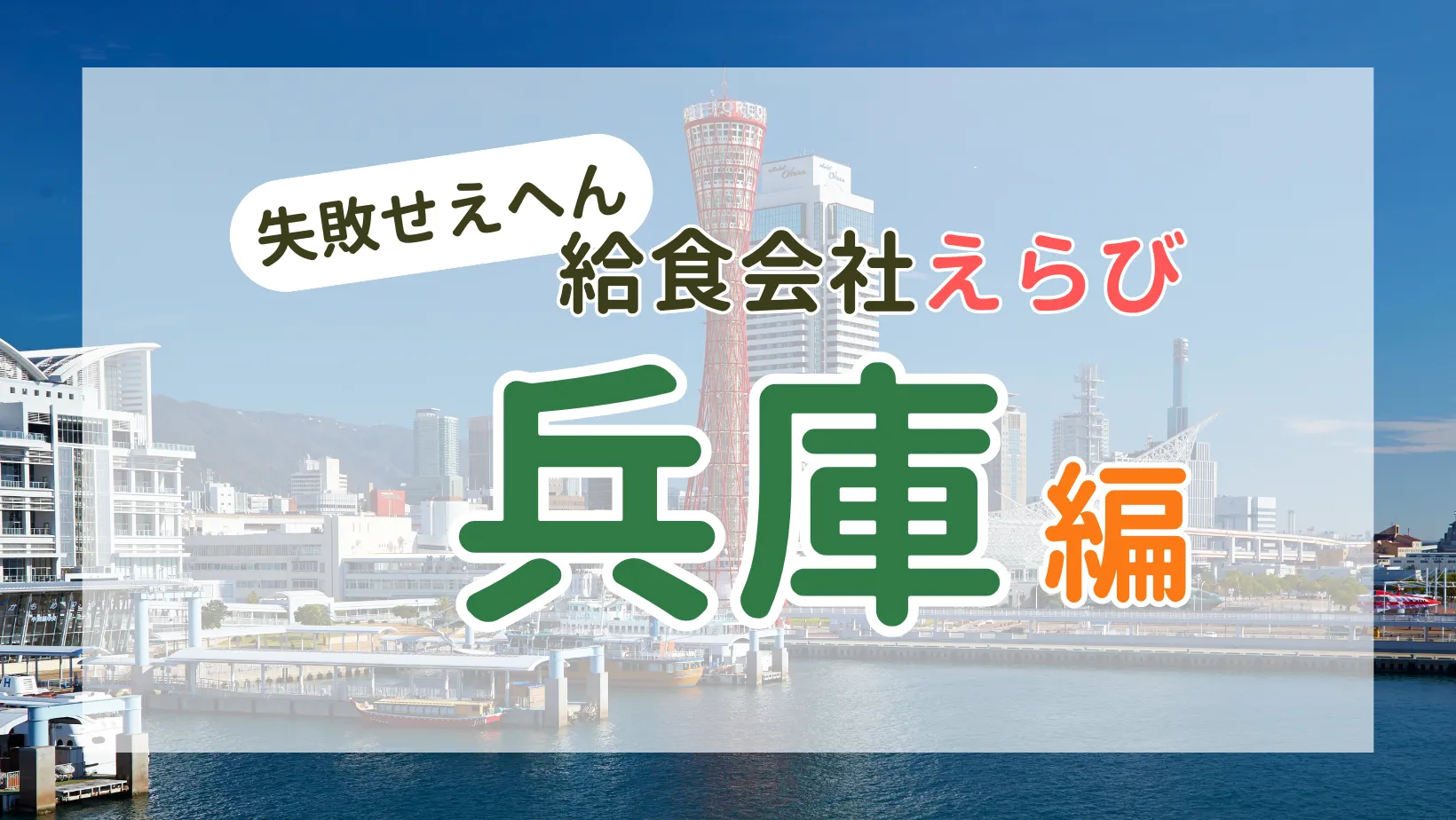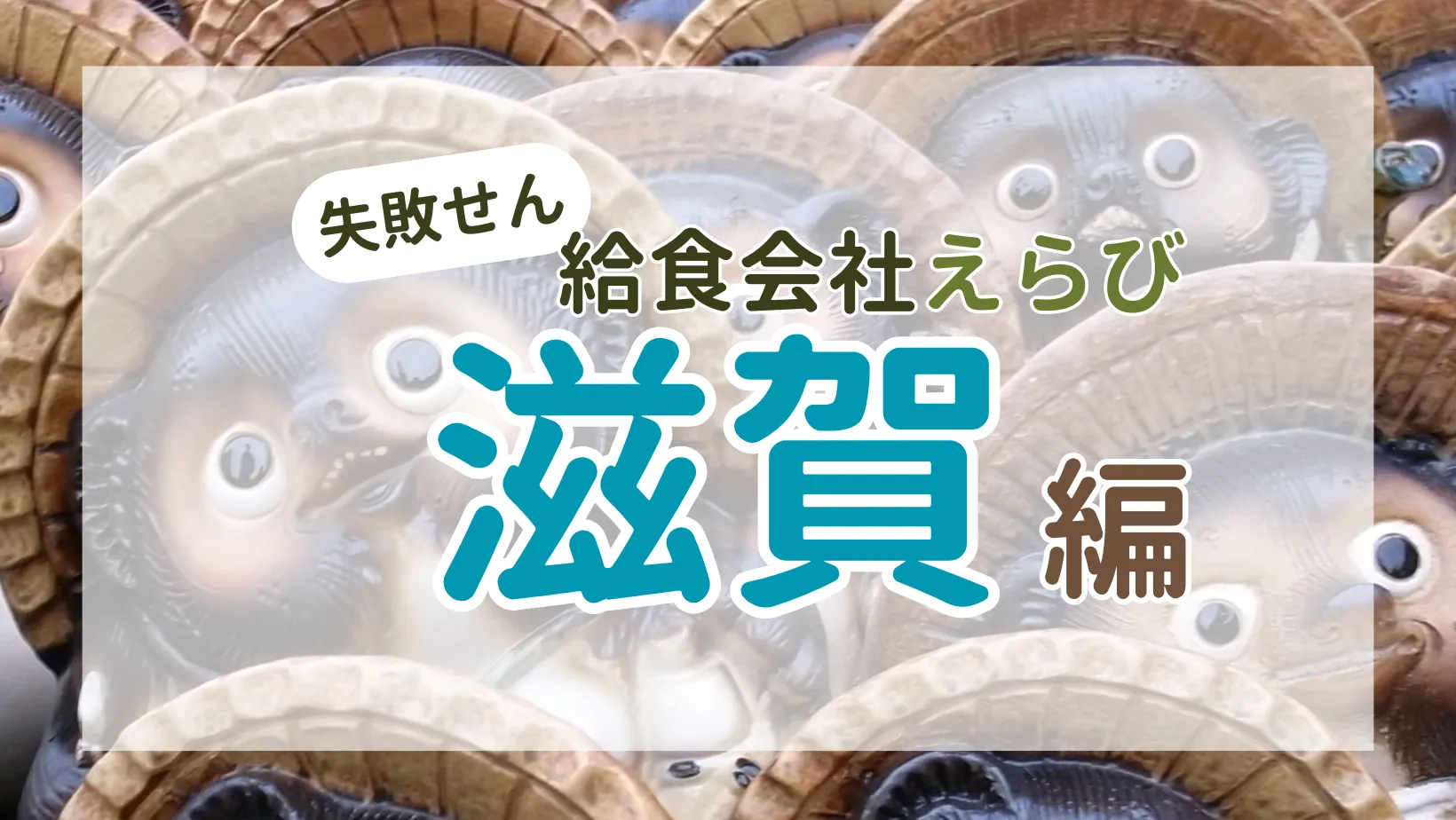食育ピクトグラム「テーマ1 みんなで楽しく食べよう」を詳しく知ろう!


日常生活のなかで欠かせない「食べる」習慣を、どのように形作っていくのか――。今、農林水産省を中心に、こうした「食育」への取り組みが盛んになっています。12のテーマで作られている、食育ピクトグラムもそんな取り組みの一つです。
この記事では、食育ピクトグラムの「テーマ1」にあたる「みんなで楽しく食べよう」について解説してきます。近年の共食の傾向や、「みんなで食べる」ことがもたらすメリットなどについて、詳しく見ていきましょう。
この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム
名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。
1.みんなで食べる機会とその推移
まずは、農林水産省が公表する「食育に関する意識調査報告書」をもとに、共食の習慣がどのように推移しているか見ていきましょう。
(1)家族との「共食」はやや減少傾向に
家族と一緒に食事を摂る頻度について、「ほとんど毎日」と答えた人が多く、過去10年間では次のように推移しています(※1)
| 朝食 | 夕食 | |
| 2022年 | 45.3% | 64.6% |
| 2021年 | 49.7% | 67.7% |
| 2020年 | 56.6% | 67.6% |
| 2019年 | 57.3% | 67.2% |
| 2018年 | 60.2% | 73.8% |
| 2017年 | 57.8% | 66.5% |
| 2016年 | 54.5% | 64.0% |
| 2015年 | 58.9% | 65.0% |
| 2014年 | 48.2% | 56.2% |
| 2013年 | 53.5% | 60.1% |
| 2012年 | 60.3% | 71.6% |
このデータから、2020年まではほとんどの年で、朝食・夕食ともに半数以上が家族と一緒に食事をとっていたことがわかります。
一方、2021年以降は夕食の共食率は維持しているものの、朝食を一緒に摂る家庭が減少傾向に。2022年だけで比較しても、前年よりも共食率がやや下がっていることがわかるでしょう。
(2)20~50代は家族との「共食」頻度は少なめ
農林水産省が公表する「平成29年度 食育白書」によると、家族と共食する頻度は20~50代で低い傾向にあるといいます(※2)。
一方で、家族と食事をすることが重要だと考える方は、すべての年代で約9割にものぼったそうです。その理由には、家族とコミュニケーションがとれることや、楽しく食べられることが挙げられています。
このことから、、家族と一緒に食事をしたい思いがあっても、働き世代にとっては共食が困難になっている様子が伺えます。
(3)「共食」が難しい理由とは
2018年の「食育に関する意識調査」では、共食が難しい理由についても公表されています。その結果は、以下のとおりです(※3)。
| 自分または家族の仕事が忙しいから | 83.8% |
| 自分または家族の学校が忙しいから | 3.5% |
| 自分または家族の塾や習いごとで忙しいから | 2.8% |
| それぞれの趣味やつきあいで忙しいから | 2.8% |
年代別にみると、20~39歳の働き世代では9割以上が「自分または家族の仕事が忙しいから」と答えたとのこと。子どもを持つ人も多い世代では、仕事の忙しさが共食を困難にする要因となっているようです。
一方で、「自分または家族の学校や塾、習いごとが忙しい」と答えた人の多くが40代女性でした。子どもが小中学生になると、部活や塾といったそれぞれの予定によって共食が困難となる家庭もあるようです。
2.「みんなで食べる」ことの効果
みんなで食べる「共食」には、さまざまなメリットがあります。ここからは、共食がもたらす効果について見ていきましょう。(1)コミュニケーションの活性化
食事を皆で食べるメリットには、コミュニケーションの活性化が挙げられます。実際に農林水産省の「食育に関する意識調査(平成30年3月)」でも、約8割の方が家族との共食のメリットにコミュニケーションを挙げています(※4)。
その日の出来事を話したり、悩みを相談したりするときにも食事の場は最適です。同じ食事内容でも、誰かと一緒に食べたほうが美味しく感じることも少なくありません。栄養を摂るだけでなく、コミュニケーションを図る機会としても、共食は重視されています。
(2)栄養バランスが良くなる
一人で食事を摂る「孤食」の場合、多くの人が自分の食べたい料理を選びやすいといわれています。そのため、栄養バランスも偏りがちです。一方で、誰かと一緒に食事をするときには、健康や栄養面を考えながら食品を摂る傾向が見られやすいといいます。こうしたことから、共食には栄養バランスが良くなるというメリットがあると考えられるでしょう。
また、一人で食事を摂ると会話をしないため、「早食い」になりがちです。早食いだと、食欲のコントロールも間に合わないため、つい食べ過ぎてしまうこともあるでしょう。こうした習慣は、将来の健康にも影響してくるため、注意が必要です。
(3)規則正しく食事を摂れる
共食のメリットには、規則正しく食事を摂れることも挙げられます。特に、共食が多いと、幅広い年代で朝食の欠食が少ないといいます。また、乳幼児では、食事と間食の時間が規則正しくなりやすいのだそう。
このように子どもにとっては、生活のリズムを身に付けていくうえでも、共食が役立ちます。規則正しい食事から、健康的な食事習慣を身に付けていきましょう。
3.世代別みんなで食べるシーン例
共食の習慣は、世代別でも違いがあります。
たとえば、「食育に関する意識調査報告書(平成30年3月)」によれば、20~39歳までは約6割の方が「平日の昼」に共食をすることが多いといいます(※5)。食事をともにする相手は、半数以上が「職場の人」とのこと。若い世代は、平日昼がみんなで食事を摂りやすいシーンだといえるでしょう。
また、70歳以上の方も男女ともに半数以上が共食すると回答しています。しかし、食事をともにする相手はほとんどが家族。すでに退職している人も多いため、共食のスタイルも年齢によって変わっていくことがわかる例でしょう。
このように、世代別で誰と食事をともにするかは変化していきます。そのため、そうした変化のなかでいかに楽しく食事をしていくか食育のなかで伝えていくのも大事になるでしょう。
たとえば保育園では、友達や先生と会話しながら食べることで話すことの楽しさを知り、食事の盛り付け、片付けを通して達成感や大変さを学ぶ、といった食育が展開されています。
また、食育は高齢者施設でも推進されています。厚生労働省では2016年度に「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理の在り方検討会」を開催し、施設内の配食には低栄養予防・フレイル予防が期待されると考え、配食事業者向けにガイドラインを作成しているほどです(※6)。
4.楽しく食べるコツ
ここからは、毎日の食事を楽しく摂るコツについて見ていきましょう。
(1)ゆっくり食べる
体が満腹だと感じ始めるのは、食事スタートから20分ほど経ってからだといわれています。そのため、ゆっくりと食事を摂ることは、しっかりと満腹感を得るためにも大切な行動です。
また、食べる順番も重要です。お味噌汁やスープなどの汁物や、野菜から食べ始めると空腹感が満たされるため食べ過ぎを防げます。ご飯などの炭水化物は、急激に血糖値を上げやすいため、最後に食べたほうが体への負担も少ないでしょう。
(2)噛むことに集中する
最近は、スマホやテレビを見ながらの「ながら食べ」をする人も増えています。何かほかの作業をしながら食事を摂ると、食べる行為に集中できないもの。そうすると、満腹感を得ることも難しくなります。
そのため、食事を摂るときには、噛むことに集中するのも大切です。しっかりと噛めば、食べ物をのどに詰まらせる心配もありません。つい早食いになりやすい方は、一口食べたら箸を置くと、噛むことに集中しやすいでしょう。
(3)感覚を研ぎ澄ます
満腹感を得るためには、食事の感覚を研ぎ澄ませることも大切です。口に含んだ食事の食感や味わい、コリコリとした音など、聴覚、味覚、嗅覚をフル回転させると得られる情報はたくさんあります。
「実況しながら食事を摂った」という研究データによると、食べる瞬間の感覚をより強く意識できたといいます。もちろん、毎回の食事を実況する必要はありませんが、食べることに集中すると、これまでには得られなかった情報にも気付けるでしょう。
5.「共食」で美味しく楽しい食事を
誰かと一緒に食事をする「共食」は、健康的な生活を送るうえでも大切な習慣です。特に、生活習慣の構築段階である子どもたちにとっては、将来のベースとなります。一方で、働き世代の家庭では、共食をしたいと思っていても実践できていないケースも少なくありません。
共食は家族に限らず、学校生活のなかでも実践できる習慣です。また、給食は食育の一環ともいわれています。子どもたちにとって美味しく楽しい習慣が作れるよう、名阪食品では給食での工夫に力を入れていきたいと思っています。 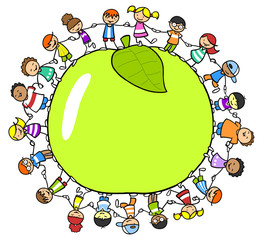
無料資料ダウンロード

献立写真集の資料を
ダウンロードいただけます
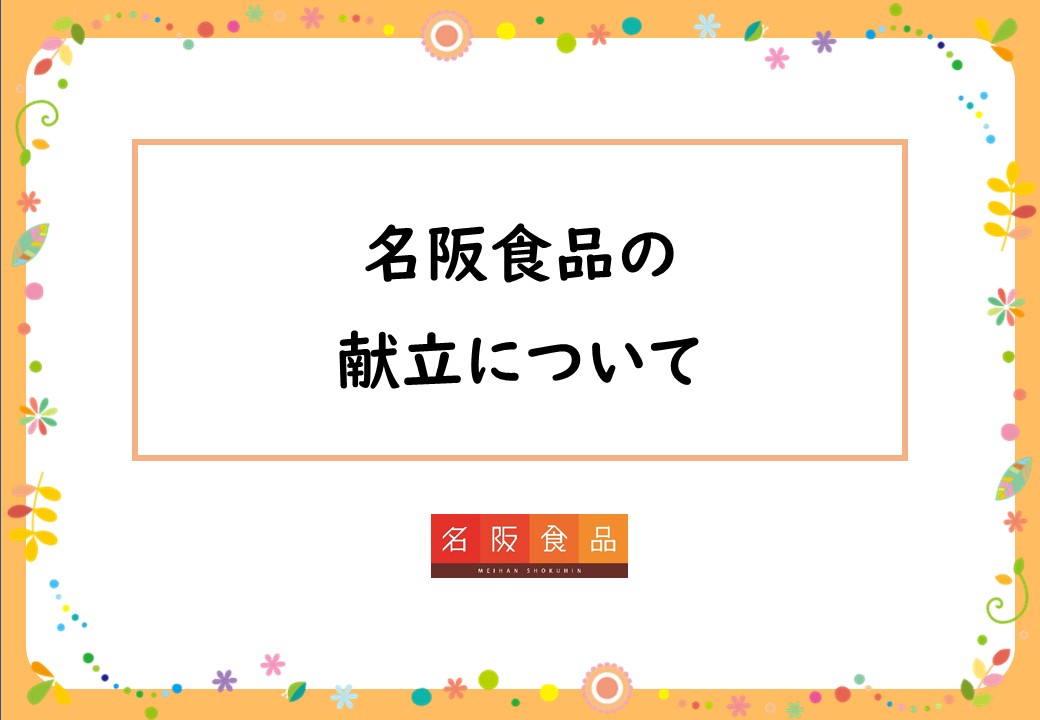
名阪食品の献立についての資料を
ダウンロードいただけます
無料資料ダウンロード
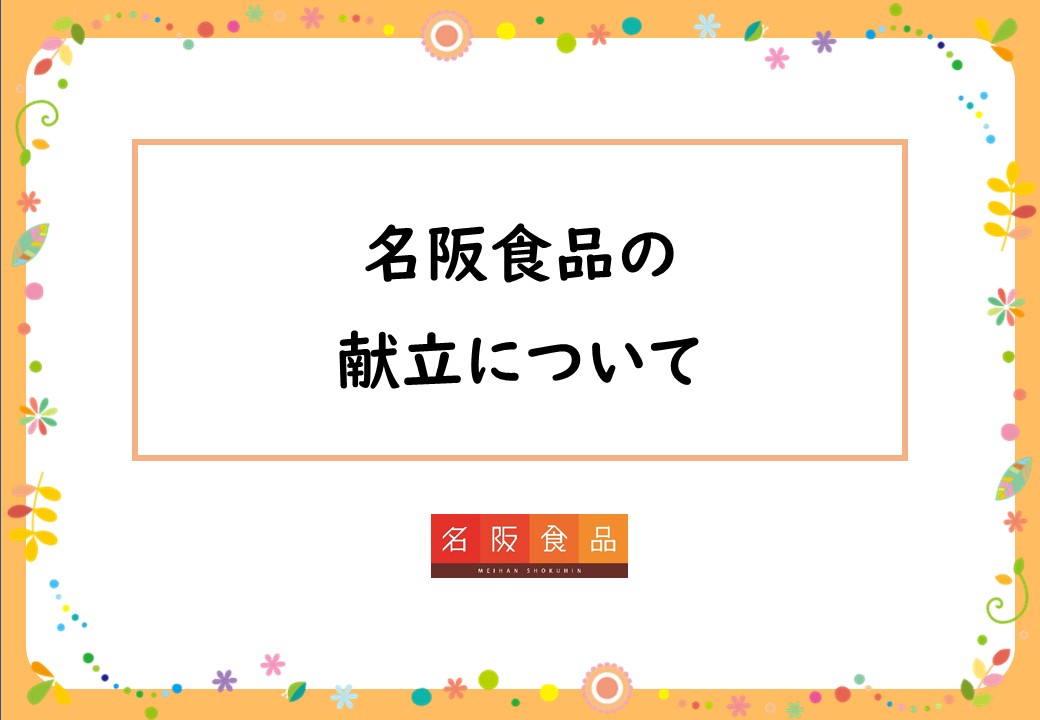
名阪食品の献立についての資料を
ダウンロードいただけます

食育実施例集の資料を
ダウンロードいただけます
【出典】
※1農林水産省「食育に関する意識調査報告書HTML形式(平成24年3月~令和4年3月)」
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki/r04/3-3.html
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki/r03/3-3.html
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki/r02/3-3.html
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki/h31/3-3.html
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki/h30/3-3.html
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki/h29/3-3.html
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki/h28/3-3.html
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9929094/www8.cao.go.jp/syokuiku/more/research/h27/3-4.html
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9929094/www8.cao.go.jp/syokuiku/more/research/h26/3-2.html
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9929094/www8.cao.go.jp/syokuiku/more/research/h25/3-5.html
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9929094/www8.cao.go.jp/syokuiku/more/research/h24/3-5.html
※2農林水産省「平成29年度 食育白書 2 家族と一緒に食べる食事の状況と取組」
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wpaper/h29/h29_h/book/part1/chap1/b1_c1_1_02.html
※3※4農林水産省「食育に関する意識調査報告書(平成30年3月)」
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki/h30/3-3.html
※5「食育に関する意識調査報告書(平成30年3月) 図3 - 1 一緒に食事をする人」
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki/h30/zuhyou/z3-1.html#h3-1-1
※6農林水産省「平成29年度 食育白書 4 高齢者に対する食育推進」
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wpaper/h29/h29_h/book/part2/chap3/b2_c3_2_04.html